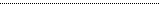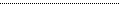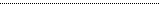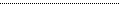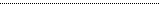|
|
2026.02.23:衆院選に想う
|
※1:
INAX BOOKLET「学校建築の冒険」。
1988年9月発刊。
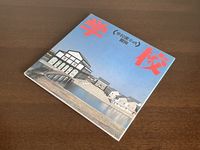
INAXギャラリーでは企画展のたびに同様のブックレットを編纂。
どれもとても内容が充実していて、全て読破すれば建築への造詣も相当深まる筈だが、如何せん私は何に対しても中途半端ゆえ・・・。
|
|
|
先般執り行われた衆議院議員選挙の・・・などと書き始めると、個人的な政治信条について滔々と語るつもりか、などと思われてしまうかもしれぬ。
そうではなくて、話したいのは投票所のこと。
私の居住地の場合、最寄りの公立中学校がいつもその会場に使われる。
数年前に校舎が建て替えられたばかりで、真新しい建物はRC造ながら内装にたっぷりと木材が使われている。
今どきの傾向なのだろう。
建て替え前に比べ、校舎の規模は大幅に縮小。
これも、対象学区の少子化の進行が可視化された今どきの傾向なのだろう。
容積が減った分、土地利用に余裕が生まれ、前面道路から十分な引きを確保したアプローチの途上には、十分な緑地とポケットパークが設けられている。
以前の校舎は、土地利用上確保可能な校舎の容積を最大限捻出。
そのボリューム内に所与の学校機能をぎっしり詰め込んだ印象であった。
土地の高度利用のためか、校舎の最上階に体育館を設置。
直下には教室が配されていたが、体育館使用時の音や振動の影響はどうだったのだろう。
例えば中間ピットを設ける等、何らかの対策がとられていたのか。
何せ旧校舎の竣工は昭和半ば。
激増する生徒数に対し、必要な諸室を確保するのに精一杯。
教育施設としてのアメニティなど、二の次であった可能性もあろう。
近傍に、同じ構成の中学校校舎が現存する。
往時の管轄行政の標準設計だったのだろうか。
私が通った小学校や中学校の校舎も、直線配置された廊下の片側に同じ規格の教室が淡々と並ぶ無味乾燥とした建物だった。
しかし卒業して数年後に別の敷地に移転。
その頃教育施設への新たな試みとして採用されつつあったオープンスペースを積極的に取り入れた新進の校舎へと建て替えられた。
同じ時期、例えばINAXが自ら運営するギャラリーにて「学校建築の冒険」と題する企画展を開催。
学校建築に関する新たな取り組み紹介すると共に、独自の冊子※1も発刊している。
教育施設に対する建築計画側からの提案、あるいは新たな試みの萌芽。
ちょうどそんな時期であった。
しかし、学び舎に対する評価は、そこで繰り広げられた体験と混然一体となった記憶に左右される。
何の変哲もない空間や設えやディテールに様々な想いが付着し、物理存在としてのそれ自体の在り姿を超えた次元で個々人の価値判断に接続する。
投票所として使われた木質感たっぷりの先進の校舎と、そうではない私がかつて通っていた無機質な校舎。
双方の差異が諸々の記憶に与える影響は果たしてどの様なものだろう・・・なんてどうでも良いことを考えながら選挙権を行使し、投票所をあとにした。
|

|
|

|
|
|
2026.02.17:(仮称)水上温泉街再生プロジェクト
|
|
※1:
|
|
|
新建築の先月号(1月号)に載せられた掲題の記事に興味を持った。
十年以上前の今の季節、初めて水上温泉を訪ねている。
無理矢理休暇を取り、気分転換を求めて赴いた同地は、意外性に満ちていた。
まずは宿泊先。
都度異なる意匠によって増築に増築を重ね肥大化した内外観は、それ自体が混沌とした一つの都市の様相※1。
今現在の姿に至った過程に強い関心を持つ。
|
 外観。
左下に僅かに写っている渓流は利根川。
この斜め向かいで、掲題のプロジェクトが進行している。
外観。
左下に僅かに写っている渓流は利根川。
この斜め向かいで、掲題のプロジェクトが進行している。
|
|
|
しかしそれは宿泊先のみならず。
案内された客室からは、同じ様に増改築を繰り返したと思しき類似施設が群を成す様子が利根川の渓流を介した対岸沿いに伺える。
いずれも昭和の半ばから後期にかけて施設の拡充が行われたものと思われる。
往時の観光ブームに乗り、競うように事業規模の拡大を図ったが、過度の肥大化が価値観や嗜好の変化への対応を困難にしたのか。
営業しているのか否か定かではない建物が散見される状況に。
同様の様態が、館内の露天風呂からも確認された。
渓流に面した対岸の崖地にへばりつくように並ぶ別の宿泊施設は、明らかに廃墟。
営業を断念してから久しい様子で、客室のバルコニーを器用に行き交う野生のニホンザルが数匹目視された。
個人的には味わい深い風情としてそれらの景観を堪能したけれど、ほかの宿泊客にとってはどうなのか。
いまや深山幽谷を堪能できる観光地など稀有である認識は持ち合わせていたとしても、替わりに眺める景観が廃墟群とあっては、なかなかに濃厚な物見遊山との印象を持つ人々も少なくは無かろう。
以降、温泉では無く、街並み探索を目的に同地を幾度か訪ねている。
廃墟然としたものも含む巨大な宿泊施設群と、どこか昔懐かしい雰囲気の商店街との対比。
建築探訪のページにも載せたみなかみ町観光会館の造形の妙。
小ぶりながらも重厚感たっぷりの浄水場の管理棟。
彩色が派手な水上寺の建物群等々。
そんな温泉地の一画で、近年になって掲題のプロジェクトが進行していたことは知らなかった。
私が宿泊したホテルと同様に度重なる増改築を行ってきたが、それによって営業の継続も建替えも除却もままならなくなってしまった建物を再活用するための取り組み。
この地の現況のポテンシャルに身の丈を合わせ、あるいは現行の法制度との整合を図るべく減築を図り、再生に必要なスケルトンのみを残した状態にまで建物を還元。
その操作が完了した状態に対して用いられた「廃墟の上棟」との表現は、詩性を帯びていて美しい。
今後、どの様な施設や空間が新たに創り出されて利活用に資するまで状況が回復されるのか。
そして、その事業スキームが、国内に大量に存する同様のストックに対する手立てとして水平展開可能な洗練を獲得出来るのか興味深い。
|

|
|

|
|
|
2026.02.10:三度目の改訂
|
|
|
|
「住宅メーカーの住宅」に登録している「ミサワホームMII型」のページを全面改訂した。
もともと2009年10月3日の雑記帳に書き綴ったものに加筆・調整等の改訂を施し、「住宅メーカーの住宅」のページ内に「不可解なモデル」と題するカテゴリを新たに追加した際に移設。
その後、2017年1月21日に改訂。
そして更に今回の改訂。
三度目ともなると、「不可解」と言いながら結構気になっているんじゃないか、と指摘されそうだけれども、全くをもってその通り。
往々にして癖が強いモデルの方が考察のし甲斐があるというもの。
かつて、2009年10月3日の雑記にも書いた。
|
こうやって書いてみると、MII型も結構面白いモデルかもしれない。
不自然に見える部位も、その背景を探れば色々と見えてくるものがあるかもしれない。
|
16年前のこの記述通り、最初は単にいびつな間取りに対し思うところをあれこれ言及しただけであった。
二回目の改訂時にはそのいびつさの要因として「ハレ」と「ケ」の視点を取り入れた。
そして今回は、同社がその草創期に設計手法として様々なモデルに展開した「ジョイントスペース」の観点を加えてみた。
それぞれの解釈が正しいのかどうかは判らない。
でも、色々な捉え方があっても愉しいではないか。
それに、同社の昭和40年代から50年代にかけての各モデルを、この「ジョイントスペース」の視点で眺めてみるととても面白い。
既に2023年12月12日から三回に亘ってこの場にも書き散らしたが、そこで言及したモデル以外にも当て嵌められる概念である。
いずれ体系化を試みてみたいなどと思うが、そこは個人サイトの気まぐれなところ。
いつ実現するか私にも判らない。
最初は、MII型ではなく、当該サイト開設時から公開したままとなっている「ミサワホームMIII型」のページの改訂を考えていた。
その際に、同社が1969年に発表したホームコアに(恐らくは)端を発する「ジョイントスペース」の構成原理を起点に幾つかのモデルに言及した後、それらを踏まえてMIII型に繋げる流れを目論んだ。
しかし前段としてのMII型までの記述が随分と長くなってしまった。
というよりも、MII型の内容が前段ではなく本筋のボリュームに肥大。
加えてMIII型について書くと、主題がどちらなのか判らなくなりかねぬ。
そんな経緯から、MII型のページ改訂と相成った。
当初の予定であったMIII型のページも手を入れねばと思うのだが、これもいつ実現するか判らない。
|

|
|

|
|
|
2026.02.03:書籍「はてしなき現代住居 1989年以後」
|
|
|
|
平成時代の住宅史を取り纏めた書籍。
建築家や研究者等、様々な識者が論稿を展開している。
第一章は、総論。
近現代の国内の住宅史がコンパクトに分かり易く纏められている。
文字通り、“総論”だ。
続く第二章、「1989−2019の住居50選」は、如何なる指標で50の住宅が選ばれたのか。
建築家の作品に偏重している感が否めぬ。
個々には時代背景を踏まえた有意な提案・提言がものの見事に空間化されているのかもしれぬ。
しかし、特殊解に過ぎる印象のものも多数。
果たしてそれらが、時代精神の表象として選択される理由となり得る哉。
むしろ例えば、不動産事業に軸足が置かれたタワーマンションやミニ開発戸建てだって、平成期に過剰化し、そして今もなお加速度を伴って進行中の“はてしなき”狂気として、十分に時代を読み解く対象となり得ますでしょうに。
50選の中には、ハウスメーカーの住宅も一件だけ取り上げられている。
積水化学工業のセキスイハイム。
年初に私もこの場に工業化住宅という側面でこのモデルに対し肯定的な書き込みを試みた。
しかし住宅産業からの唯一の選択が、なぜハイムなのか。
しかも内容はZEH。
環境配慮ならば、先鋭的な試行モデル等、もっと取り上げるべき事例が他にもあろう。
あるいは平成時代の外せぬ事象として、例えばデフレスパイラルのどん底にあって市場にインパクトを与えたローコストモデルとか、共働き世帯数の増加や男女雇用機会均等法の改正等に伴い一般化してきた「家事シェア」の価値観をプランに反映させたモデル等、他に挙げるべき事例が多々あるのではないかとも思うけれど。
そんな訳で、第二章はやや腑に落ちぬまま読み進めてしまったが、続く第三章はとっても面白い。
住まいに纏わる諸相が、それぞれの分野の専門家によって鋭く言及されている。
後世の歴史家たちは、大きな変化を伴いながら複雑かつ多岐に広がる現代の住文化をどのように捉え、論評することになるのだろうか。
大きな変容の渦中にありながら、しかし昭和の後期から今に至るまで、不気味に変わらぬ住まいの姿もある。
片廊下型の集合住宅における3LDKの住戸。
いわゆる「マンション田の字」と呼ばれる間取りだ。
否、全く変化が無いわけではない。
和室が一室も造られなくなったとか、対面キッチンが当たり前になったとか、間口がどんどん狭隘化して廊下と見まごうばかりの細長い個室が計画される様になってきた等、僅かな変化は見受けられる。
しかし基本的な骨格は殆ど変わらぬまま、大量に建設・販売され、そして中古市場にも流通する。
既に十分コモディティ化の隘路に嵌り込んだそれらが、飽きられることなく購入され続ける。
あるいは売買が好調だから供給者側も連綿とそれを造り続ける。
そんな市場が、流行廃りの激しいこの国において何ゆえ数十年に亘って成立し得ているのか。
これも、「はてしなき現代住居」の一側面ではあろうか。
・・・などと能天気に論い出すと、とてもじゃないが一冊の本には納まり切らなくなるのだろう。
それこそが、“はてしなき”所以。
|

|
|

|
|
|
2026.01.27:「北海道総務部総務課第一車庫公宅」に纏わるメモ
|
|
※1:
|
|
|
先月、建築探訪に載せている掲題の建物のページを改訂した。
同ページはこのサイトを開設した当初から掲載しているから、19年を経ての改訂となる。
近年になって、往時は解らなかった当該建物の来歴を様々知り得る機会を得た。
その経緯も含め、この異形建築に纏わる初見から今までの事々を綴る形で、文章を全面的に改めた※1。
|
改訂にあたって、雑記帳の2023年6月28日の書き込みの多くを援用した。
重複を避けるため同雑記は削除。
建築探訪のページに加筆・調整のうえ移設した旨を記した。

※2:
セミナー開催告知のポスター。
未だに所持している人など稀なのだろうな。
単に収納の奥に仕舞い込んでいただけだが、ここまで来ると個人的な人生の記録としての価値を帯び始めているのかも。

|
|
|
|
|
|
掲載した建物外観の画像を見ると、所どころに雪が残っている。
撮影したのは、当該建物の近傍にかつて在った札幌青少年センターにて1990年3月7日から18日までの日程で開催された「第一回学生建築セミナー」※2に参加していたさなかであった。
同セミナーの主催は、「建築家の卵協会」。
道内の大学の建築学科に在籍する学生どうしの横のつながりを作ろうと有志で設立した協会で、私も最年少で参加していた。
第一回目のセミナーのテーマは「現代の市場」。
衰退傾向にある市内の市場の活性化を建築の側から考えようというもの。
複数のグループを組成し、それぞれに道内の著名建築家が付いて指導。
最終日に成果物の講評会を行い、更に後日、市内のデパートの催事場で作品展示会まで行うセミナーであった。
期間中はとにかく慌ただしくて、ゆえに近傍に建つ掲題の建物に関心を寄せる余裕も無かった。
通りすがりに二枚写真を撮るのがせいぜい。
そのまま忘却に付してしまった。
協会のメンバーとして企画と運営に携わりつつセミナー自体にも参加したのだから、我ながら随分欲張ったというか、前向きで行動力があったなと思う。
でも、それが一体自身に何をもたらしたのか。
セミナーの開催は一回のみ。
協会自体も自然消滅してしまった。
今になって思えば、何かどうでも良いことに膨大なエネルギーを注ぎ込んでしまっていた様な気がしなくも無い。
|
|
※3:
|
|
|
しかしそこはそれ、昨年12月12日に言及したアンギャマンの漫画作品「ラーメン赤猫」の第135話※3で店長の文蔵さんも、
|
|
単行本第12巻所収。
|
|
|
|
|
|
と、接客術伝授のためイタリアに長期出張する店員を激励していました。
きっと、識閾下で今の自分に何らかの良い作用をもたらしている違いないとしておきましょうか。
思えば、企画会議の途中で建築に纏わる論争となり、年上の大学院在籍の面々にコテンパンにやり込められたのは、今となっては懐かしい経験。
それに、セミナーに参加するため会場に赴かなければ、近傍に建つ異形建築との遭遇は無かったかもしれぬ。
そんな事々を思い起こしてみれば、決して「無駄」の一言で片づけられはしない。
|

|
|

|
|
|
2026.01.20:奥野ビル
|
|
|
|
歴史的建造物の保全は難しい。
竣工時の様態を忠実に復元する行為は学術的にも、そしてその建物自体の価値を維持するためにも有意ではある。
しかし、建築はその時々のニーズに基づき供用されてナンボの物理存在。
その要求品質との乖離や折り合いをどう捉えるべきか。
あるいはそれ以前に、時間の経過と共に内外観に堆積されて来た風合いや表情が綺麗さっぱり洗い流されてしまった復元後の真新しい姿に何とも言えぬ思いを抱く実例には事欠かぬ。
加えて移築を伴う復元となると状況は更に微妙となる。
長年醸成されて来た周辺環境とのコンテクストと切り離されて真新しく再生されたその佇まいに纏わりつく違和感について、例えば「徘徊と日常」のページで2013年7月17日にも事例をサラリと取り上げてみた。
歴史的街並の保全などの場合も同様。
修景が施された街並みに纏わりつく舞台装置の背景の様な白々しさ。
多寡の差こそあれ観光目的と何らかの形で癒着する修景事業の帰結としてオーバーツーリズムに晒されるそれらの場所を再訪してみたいとの気分は、今のところ全く起きはせぬ。
そんな中、銀座一丁目に立地する「奥野ビル」は、奇跡的に好ましい様態を維持し続ける歴史的建造物だ。
旧名称は、「銀座アパートメント」。
経済の理論で建物が耐久消費財の如く目まぐるしく更新され、次々と自己顕示欲旺盛な商業ビルが建てられ続け雑然としたごった煮状態を呈す銀座。
その中に在って昭和7年竣工のこの建物は、極々自然な経年変化を内外観に醸しつつ周囲の風景に埋没せぬ落ち着きを持って鎮座する。
元々集合住宅として建てられ、今はアートギャラリーが多く入居する当該建物の前は幾度か往来しているが屋内に入ったことは未だに無い。
そんな館内に入居するギャラリーの一つ「Salon de la」にて開催中の版画展「Seed Stories 25_26」に知り合いが出展すると御紹介頂き、これを機に訪ねてみることに。
その前に当該ビルについておさらいしようと、大月敏雄著「集合住宅の時間」を書棚から引っ張り出す。
著者の講演会に参加した際に入手したサイン入りの書籍で、サインの脇には2007年3月10日と日付が添えられている。
既に19年が経とうとしているのだななどとしみじみ思いつつ、同書籍の中で言及されている当該ビルについて久々に読み直す。
否応なしに、建物への興味が増す。
「作品鑑賞が目的だからな」と自身に言い聞かせつつ、しかし半ばそれ以上の関心は、やはり建物。
否、そもそもアート作品の鑑賞はそれ自体のみを愛でることに非ず。
それが置かれた場所、あるいは環境と共に魅力が読み解かれるのであって、従ってそれが配された建築に関心の視線を向ける行為に何の矛盾も不合理もありはしない、などと適当に都合の良い理屈を組み立てつつ現地に向かう。
そして、堆積した時間によって造り出される奥ゆかしい空間の質と共に各作品を堪能した。
|

|
|

|
|
|
2026.01.12:孤独のグルメ年末スペシャル
|
|
|
|
年末年始に限らず、実家への帰省時は(可能な限り)デジタルデトックスに努めている。
一年のうちの何度か、その様な機会を纏まった期間確保するのも悪くは無かろう。
しかし哀しきかな。
ネットを遮断してしまうと、何をして過ごせばよいか悩んでしまう。
家の周りの散策。
ちょっと遠くに出かけてみる。
はたまた読書。
いずれにも飽き、ないしは疲れてしまうと、サテどうしたものか。
テレビを点けてもつまらない番組ばかりで、年末年始なら尚更だけれども、取り敢えず消去法で「孤独のグルメ」の再放送を視聴する。
既に風物詩の位置づけを獲得しているのか否かは知らぬ。
しかし、今回の年末年始もテレビ東京系は当該ドラマを早朝から昼過ぎまで過去放映分を一挙再放送。
何度か視ているので、今更椅子に腰かけてじっくりと堪能するほどでもない。
柄にもなく大掃除の様なことをしながら、時折眺めるといった程度に視聴を愉しむ。
過去放映の年末スペシャルも再放送されたが、個人的には2022年の北海道編は何度視ても良いと思う。
当該ドラマは、主人公の井之頭五郎さんが出先で適当な飲食店に入り、そこのメニューを独りで食して愉しむシーンをモノローグと共に流すことが主題。
ストーリー性は特に重要視されない。
ストーリーに求められるのは、その日入る店に出会うためのお膳立てでしかない。
恐らくは大半の視聴者も、そこに期待などしていないのだろう。
しかし、2022年版は珍しくストーリー性があった。
ちゃんと伏線が仕組まれ、最後に見事に回収して大団円・・・では終わらせず、また独り、小さな店で静かに食を愉しんで年末を締めくくる。
そんな組み立てがとっても良かった。
それでなくても舞台は北海道。
私のお気に入りの風景も一瞬登場したことは、ちょうど三年前にもこの場に書きましたか。
聚富海岸の段丘から厚田方面を遠望するそのシーンは、何度視てもホロリとしてしまう。
然るに、昨年末のスペシャル版はどうだろう。
先述のとおり、ストーリーは五郎さんが様々な場所を訪れるためのきっかけに過ぎぬが、それにしても今回の設定はちょっと残念ではありましたか。
食材に強い拘りを持つくせに、その調達や事前準備の段取りもロクに出来ぬ若手おむすび職人の我儘に五郎さんが振り回され続けるの図。
この若者、こんな調子では長続きしないゾ・・・などと思いつつの視聴となる。
今回は、所々で生放送が挿入される趣向。
五郎さんが奔走した甲斐あって、無事生放送中にイベント会場で配られたおむすびの具は肉そぼろ。
苦労の割にはそんなにおいしそうには見えませんでしたか。
私の場合、おにぎりの具といったら、ちょい辛めのネギ味噌が嬉しいところであったりもしますので。
|

|
|

|
|
|
2026.01.05:メーカー住宅私考_211
|
|
|
|
いつも通り、北海道の実家で年末年始を過ごす。
帰省期間中は例年に比べ明らかに少雪。
年末は、雪が降っても雨混じり。
辛うじて降り積もった雪はグショグショ。
道路はアスファルト舗装が、そして庭先は表土が広く露出する有様。
厳冬の北の風情を堪能する雰囲気からは程遠い。
年が明けて三日目になって漸く、冴えわたる氷点下の大気のもと新雪の踏み心地を愉しみながらあても無く周囲を散策する。
前にも書いたが、実家が立地するのは昭和40年代半ばに造成された大規模な住宅地。
各年代の戸建て住宅がまんべんなく建つ。
築年数を経た住まいであれば、その表層に顕れている経年変化や改修状況の確認。
新築のものであれば、どこのメーカーの仕事だろうと見立ててみる。
そんなことを愉しみつつ徘徊する中で、後者に関しては積水化学工業のセキスイハイムがやたらと目に留まる。
否、同社の直近のラインアップはよく知らないし、そもそも大して興味も無い。
でも、他社とは明らかに異なる方向性で取り纏められた外観は、容易にそれと判別が可能だ。
と同時に、一切の逡巡無きその方向性に感心させられもする。
多くのメーカーが、用いる工法の特性を活かすことなく似たり寄ったりの商品企画を展開する中にあって、積水化学工業は例外。
ユニット工法ならではの意匠の特化に矜持をもって取り組んでいる姿勢が容易に窺える。
ユニット住宅はかくあるべしという拘り。
強い信念。
過去において、その辺りに迷いが生じていた時期が無かった訳では無い。
例えば、80年代前半。
ユニット工法が持つ制約を超えて何とか普通の家らしさを目指そうと、いびつなモデルを生み出していた時期があった。
その頃のモデルについては、個人的には全く評価出来ない。
しかしながら現在、そんな逡巡は一切見受けられぬ。
工場生産された四角四面のルームユニットを縦横に積み重ねる同構法の特徴をそのまま現わしつつ、ディテールやテクスチュアへの拘りによって住まいとしての独自のかたちをしっかりと生成している。
「勾配屋根?軒の出?、そんな物が欲しかったら他社のありふれたモデルをドウゾ。」とでも言わんばかりのユニット住宅ならではの意匠の洗練がすこぶる清々しい。
勿論、同社の現在の全商品が同様の形態を纏っている訳では無いのかもしれぬ。
その辺は疎いので良く判らないけれど、少なくともその様な思想に基づくモデルを主力商品と位置付けているのは間違いなかろう。
かつて、工業化住宅の最終形態として夢見られ、数多くのメーカーが挑戦し脱落したユニット工法。
その淘汰の歴史の中で、この工法に拘り続け、他の追従を許さぬ進化を極めてきたセキスイハイム。
工業化住宅の王道を突き進んでいると評価できるのは、実は積水化学工業だけなのではないか、などと思い、且つそのデザインに感心しつつ、では好みに合うかというと、まぁそれは別問題であったりする訳ですけれども。
|