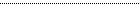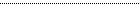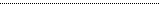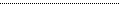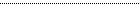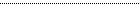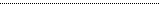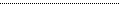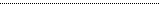|
|
2019.03.26:内と外の境界、そして可能と不可能の境界
|
※1:
 名古屋市美術館南側外観。
名古屋市美術館南側外観。
中間領域の形態操作が展開するのは、上記画像とは逆の北側。
しかし南側の意匠も隙を見せることなく手堅く纏められている様に思う。
|
|
|
埼玉県立近代美術館にて開催(会期2月2日〜3月24日)されていた企画展「インポッシブル・アーキテクチャー」を終了間際に観に行ってきた。
この手の建築を、業界では一般的に「アンビルド」と呼ぶ。
敢えてその言葉を用いず「インポッシブル」とタイトルに冠した意図は何か。
そこには、単にアンビルド作品を並べることとは異なる未完の建築に対する何らかの提示があるのだろうか。
そんなことへの興味から、同展に足を運ぶこととなった。
埼玉近美の特徴といえば、エントランス周りに計画された「中間領域」であることは改めて述べるまでもない。
設計者である黒川紀章が提言したそのタームが、開放性の高いグリッドと波を打つガラスの壁によってとても分かり易くそこに実現。
それらの設えによって、外部とは異なりながら内部でも無い曖昧な空間が確かに形成されてはいる。
 しかし、内外の緩衝エリアである筈のその中間領域の意図を知覚出来るのは、外からその中間領域に入った時だけ。
そこから更に出入口を介して屋内に入った際、その部分でウチとソトの分断を強く認識することになる。
それは、入った直後に視覚に飛び込むエントランスホールの空間構成が、いかにも普通の内部であるため。
空間の広さや奥行に対してやや低めの天井高。
あるいはその天井面は既成の吸音板を張っただけの無表情な設え。
更には、そのホール内にミュージアムショップやチケットビューローが何となく惰性で配置されてしまっている印象。
「外部」と「中間領域」で企図された曖昧な領域分けが、「中間領域」と「内部」の境界で同質なものとして成立していない。
しかし、内外の緩衝エリアである筈のその中間領域の意図を知覚出来るのは、外からその中間領域に入った時だけ。
そこから更に出入口を介して屋内に入った際、その部分でウチとソトの分断を強く認識することになる。
それは、入った直後に視覚に飛び込むエントランスホールの空間構成が、いかにも普通の内部であるため。
空間の広さや奥行に対してやや低めの天井高。
あるいはその天井面は既成の吸音板を張っただけの無表情な設え。
更には、そのホール内にミュージアムショップやチケットビューローが何となく惰性で配置されてしまっている印象。
「外部」と「中間領域」で企図された曖昧な領域分けが、「中間領域」と「内部」の境界で同質なものとして成立していない。
それは、中間領域を平面計画のみで構想してしまったためではないかなどと勝手に考える。
即ち、透過性の高い格子フレームと波打つガラス壁を設えた「中間領域」による内外の境界の曖昧化は、平面プラン上ではその意図を読み取り易い。
しかしその境界設定を断面や空間で捉えた場合、「中間領域」と「内部」の境界が如何にも連続性を欠いている。
この断面や空間も含めた中間領域の実現は、埼玉近美の六年後に竣工した名古屋市美術館※1ということになるのだろうか。
そちらの美術館に見受けられる吹抜けやサンクンガーデンを駆使した中間領域と内部の空間操作は、埼玉近美には無い曖昧性を動的且つ大胆に獲得しているという印象がある。
そんなことを考えながら企画展の展示室に歩を向けると、最初に「見えざる都市 メタボリズム編」と題するピエール・ジャン・ジル―の映像作品。
東京の現代の風景にメタボリズム作品が違和なく合成されたその映像美を見入ることとなる。
しかし暫くして疑念が湧く。
そこに描写されているのは、既に良く知られたアンビルド作品。
結局のところ、「インポッシブル」と銘打ちつつ、内容は手垢にまみれたアンビルド作品展ということなのではないかという不安。
そしてその不安というか不満は、会場を歩み進めても晴れぬ。
初見の興味深い展示も散見されるが、多くはアンビルド作品として既に幾度も建築メディアに登場しているもの。
やや肩透かしを食らった気分で歩を進めつつ、しかし順路の最後の方に展示されていたザハ・ハディッドの新国立競技場のブースで腑に落ちることとなる。
風洞試験模型等と共に展示された当該建物の実現に向けた許認可関係資料の夥しい製本群は、「ここまで準備したのに」というプロジェクト関係者達の恨み節の吐露と単純には捉えられなくもない。
しかしそれ以上に、そこにこの企画展が企図した「ポッシブル」と「インポッシブル」の境界が強く顕然している様に思えた。
そしてそんな視点でそれまで巡ってきた各作品群を今一度見直すと、また違った鑑賞が可能となりそうだ。
その境界とは一体何か。
館内のホールに据えられているエーロ・サーリネンの「ウームチェア」に深々と身を沈めながら、企画展鑑賞後に暫し思索を巡らせることとなった。
同展は、今後新潟や広島を巡回予定。
|

|
|

|
|
|
2019.03.20:CYBORG009 CALL OF JUSTICE
|
|
|
|
ANIMAXにて「CYBORG009 CALL OF JUSTICE(以下、COJ)」を視聴する。
三章に分けて映画館で公開された2017年の作品。
それを全12話に再編集して放映された。
映画公開時に映画館に出向く気が起きなかったのは、同じ製作会社の手に拠る前作「009 RE:CYBORG」が難解で訳の判らぬ作品という印象に留まったため(と言いつつ、以前この場にレビューを書いたが)。
前作は作画はとてもきれいだし現代風にリメイクされたキャラクターデザインも良かった。
しかしストーリーの結末はその解釈を視聴者の読解力に委ねてしまったという印象。
それは私が同作品の世界観を理解出来ていないために持ってしまう印象なのだろうか。
なにせ長きにわたって数々制作されてきたシリーズ作品の中で、私がまともに目を通したのって原作の第一巻のみ。
そういった初心者には伺い知れぬ深淵が作品のそこかしこに寓意されているということなのだろうと受け留めるしか無かった。
ならば、新作だって拝んでも仕方があるまいと思ったのだけれども、偶然目にしたレビューの中に「MMDみたいな作画」といった言葉を見つけちょっと興味を持った。
かのProduction IGが手掛けるMMDみたいな作画ってどんなものだろう。
ということで、ANIMAXでの放映を機に視聴した次第。
そのフル3DCGアニメーションは、なるほど確かに動きに違和を覚えるし背景を含めた全ての描写がなんだかとてもチープ。
しかしそれをもってMMDみたいとするのは、MMDやその関連ツールの開発・公開に携わる人々、そしてMMDerに対して失礼というものであろう。
否、失礼と思いながらも、しかしやはりMMDっぽいカモなどと逆に親近感を覚えつつ、各話を視聴することとなった。
ストーリーの流れは、前作に比べるとエンタテインメント性が強く出ているという印象。
でも、結末は「アレッ、これで終わりなの?」といった印象でしたか。
前作ほどでは無いものの、何となく取り残されてしまった感。
しかし、取り敢えずは結末に描かれた国連軍の五十嵐威の短いセリフに全てを押し込んだのだろうと個人的には解釈することにした。
つまり、各地で繰り広げられた00ナンバーサイボーグとブレスド、そして国連軍との壮絶なバトルの後始末と、その後の展開。
それらを短いセリフの中に読み取ることで、ラストシーンのシルエットを自分なりに理解することが出来そうだ。
それは例えば、同じくProduction IGがかつて手掛けた「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の結末にも通じる。
同作品で描かれた、「笑い男事件」に端を発して暴かれた政界スキャンダルに絡む公安9課の「後始末」に似た展開が組み立てられる可能性。
結果、公安9課は「名を捨てて実を取る。これで俺達は晴れて、世間には存在しない攻性の組織に戻ったって訳だ。」というバトーのセリフに繋がった。
シルエットのそれも、同じ隠喩を込めたのではないか。
そういえば、同作品の監督は、今回のCOJの総監督でもありますか。
であるならば、ラスボスであるところの「エンペラー」とのバトルに長丁場を費やすより、その「後始末」に一話を充てても良かった様に思う。
バトルのさなか、エンペラーが「青臭い」と評した009の正義感丸出しのセリフを散々聞かされるよりはネ・・・。
青臭いと言えば、009って実年齢は何歳の設定になるのだろう。
勿論それは不問に付すべき事項なのだろうけれども、「009 RE:CYBORG」ではその辺りのことが考慮されてキャラクターデザインや立ち居振る舞いに微調整が加えられていた様に思う。
しかし、COJではそういった配慮は特に無し。
RE:CYBORGよりも幾分若返った印象(但し、001とギルモア博士は除く)。
と同時に、立ち居振る舞いについても、これが半世紀にわたって人類の危機を何度も救ってきた百戦錬磨の「戦鬼」達なのかと首を傾げてしまうリスク管理のお粗末さが散見されぬ訳でも無い。
そこら辺が、長寿作品を映像化する際の難しいところでもあるのだろう。
すなわち、現代という時代における往年のヒーロー達の立ち居振る舞いの在り方と経時との整合。
あるいは更に、マニアたちを納得させ得るだけの過去のシリーズ作品へのオマージュの埋め込みと、逆に初心者にも訴求し得る作品そのもののストーリー構成とのバランス。
その点において、例えば同じく長寿作品であるルパン三世の近作「part5」は巧く纏めていたことになるのだろうナと改めて思う。
|

|
|

|
|
|
2019.03.12:メーカー住宅私考_102
|
|
|
|
このシリーズの第101回(2019年2月4日記載)において、「ミサワホーム555」の建築事例について言及した。
その際、同事例の隣にミサワホームが発売した同じくユニット工法を用いた「NEAT EMBLEM」が建っていることも紹介した。
中古販売サイトによると両棟とも売り出し中。
どうやら二棟は同じ敷地に建つ同一所有者の住まいであった様だ。
その事情というか経緯については当然知る由も無いが、少なくとも二つの流れは容易に邪推出来る。
つまり、所有者がミサワホームの関係者かその親族の住まいとして建てられた可能性。
両棟に用いられているユニット工法の開発に携わっていた方が建てたものであるならば、尚面白い。
もう一つは、同社のユニット工法に強い関心を示し、且つ惚れ込んだいわばミサワマニアの方が建てたものである可能性。
マーケティング用語に「イノベーター理論」というものがある。
新商品に対する購買層の属性を5つに分類したものだ。
その内訳は以下の通り。
|
1.
|
イノベーター(革新者)
|
|
2.
|
アーリーアダプター(初期採用層)
|
|
3.
|
アーリーマジョリティ(前期追随層)
|
|
4.
|
レイトマジョリティ(後期追随層)
|
|
5.
|
ラガード(遅滞層)
|
1.は新しい技術や製品への興味や憧れがとても強く、それらへの購入にすぐ動く購買層。
逆に全く興味を示さないのが5.の属性。
国内の住宅産業草創期においても、イノベーターにあたる購買層が存在していた様だ。
例えば、矢島鈞次監修の書籍「住宅革命進行中―積水化学ーハイムに賭けるフロンティア集団」の第5章に「ユーザー第一号は機能美にほれた」という項が設けられ、積水化学工業のセキスイハイムM1の第一号契約者のエピソードが記されている。
精神科医であったその「イノベーター」は、1970年に東京晴海で開催された第一回東京国際グッドリビングショーに出展された同モデルのプロトタイプモデルを観て、程なく契約。
その後も後継モデルであるMRに住み替え、更にはハイムでアパートまで建てたという。
そのエピソードの締めくくりには、
|
セキスイハイムには、(中略)“ハイム党”とでもいえる熱烈なハイムファンがついているのである
|
とある。
あるいは、新建築1984年4月臨時増刊号「住宅の工業化は今」の冒頭に収録されている内田祥哉と三澤千代治の対談の中で、三澤氏の以下の発言がある。
|
古いお客様というのは、新しいもの好きで、ある程度覚悟して買っていただいているようなところがあって、ファンになっていただきやすかったですね、
「壊れてしまったものは、しょうがない。もうちょっとしっかりやってくださいよ」というようなことで、そしてまた別のお客様を紹介してくださったりして、本当にありがたいと思っています。
|
|
甘えていたわけではないですが、何かあっても許してもらえたところがありました。
もちろん意見はいろいろありましたが、パイオニア精神というのか、そういったお客様が多かったですね。
|
それが全てではないにせよ、その様な人々によってベンチャー企業同然であった各メーカーが育まれ、市場も徐々に拡大した。
とするならば、そんな「イノベーター」達について事例を追跡してみることも、日本の住宅産業史における視点の一つとしてアリなのかもしれぬ。
そして例えば冒頭に記したミサワホームの中古事例に纏わる後者の邪推も、「イノベーター」ということになろう。
つまり、同社のユニット工法の初期に属するモデルである「ミサワホーム555」に先ず飛びつき、それに深く惚れ込んだ上で、更にその後に「NEAT EMBLEM」も所有することとなった可能性。
蛇足だが、先述の属性に従うならば、私は完璧な「ラガード」である。
|

|
|

|
|
|
2019.03.05:翔んで埼玉
|
|
|
|
絢爛にして面妖。
そして背景に黒ベタを多用した繊細で几帳面な描写。
耽美の王道を地で行くその美麗な作画にブラックなギャグが疾走感たっぷりに絡む。
魔夜峰央の(かつての)作風に対しこの様な印象を持つのは、80年代に「パタリロ!」や「ラシャーヌ!」を読んでいた影響。
一方、掲題の作品は読んでいない。
同時代の作品として同じようなテイストで描かれつつ、しかしその内容は埼玉を徹底的にこき下ろした過激なものらしいというのは近年になって知ったこと。
そんな「問題作」の実写映画化ということで興味を持ち、近所のシネコンに歩を向けた。
その内容は(くどくなるが、「かつて」の)魔夜ワールドそのもの。
よくぞここまで徹底的に映像化できたものだと感心しつつ、更には壮大で荒唐無稽でバカバカしい虚構を大真面目に怪演するキャスト達の力量にも感嘆する。
こんな学生がいる訳ねぇだろう!と突っ込むべき筈のところを、しかしその絢爛たる画面の中で何ら違和感無くその役どころを演じ切るGACKTや二階堂ふみらの立ち居振る舞いに感服しつつ、大いに愉しませてもらった。
そして、内容が内容だけに批判が巻き起こるかもしれぬというリスクの低減を図るために物語の組み立てについて周到に配慮されていることが読み取れ、最初から最後まで安心して楽しむことも出来た。
ということで、以下はネタバレにならぬ程度に映像の中に出て来た建造物に対するコメントを二点。
Z組の教室
物語序盤の舞台となる名門・白鵬堂学院の片隅に設けられた別棟の教室。
その設えは、宮殿かと見紛うばかりの贅を尽くした豪奢な校舎施設群の中にあって様相を全く異にする酷く粗末なもの。
そこは、なぜか入学が許可された少数の埼玉県出身者のみで構成されるZ組を隔離することを目的とした専用の教室(というか、小屋)。
しかし粗末な小屋という設定ならば倒壊寸前の掘立小屋にでもすれば良いところを、大谷石による組積造の小屋としている。
存外それは、35年ローン組んで買ったはいいけれど20年でダメになってしまう見てくれは綺麗だけど実は中身ペラペラな巷に溢れるローコスト建売住宅の類いなんかより余程頼もしそうだ。
漫画家には、どんなに豪華な空間を描いても貧相な絵になる作家と、それとは逆にどんなに貧しい空間を描こうとしても貧しく描き切れぬ作家がいる。
自分は後者だといった旨のことを、大昔のインタビュー記事の中で魔夜峰央御本人が述べていた。
粗末な小屋だからといって徹底的に粗末にするのではなく、その少し手前に踏み留める設定。
それは、魔夜ワールドの現実化の一端なのかもしれぬ。
埼玉解放戦線の拠点
終盤に登場するそのシーンのロケ地が首都圏外郭放水路の調圧水槽であることはすぐに判った。
 当該施設は首都圏の治水を目的に埼玉県内に整備されたもの。
首都の水防の要を埼玉が担う。
すなわち埼玉あっての首都機能の保持ということに他ならぬ。
そんな巨大インフラ施設を当該組織の拠点として設定したのは、この作品が埼玉を貶めるものではなく逆に賞賛を寓意するためのものであるなどと解釈するのは無理矢理過ぎるか。
当該施設は首都圏の治水を目的に埼玉県内に整備されたもの。
首都の水防の要を埼玉が担う。
すなわち埼玉あっての首都機能の保持ということに他ならぬ。
そんな巨大インフラ施設を当該組織の拠点として設定したのは、この作品が埼玉を貶めるものではなく逆に賞賛を寓意するためのものであるなどと解釈するのは無理矢理過ぎるか。
この作品は、関東の各都県民どうしが互いに抱く感情の機微を、程度の差や個人差こそあれブラック・ユーモアとして閾下のうちに共有出来る者が自虐性も含めてその内容を愉しめるといった面がある様に思う。
そうではない人々にとって、果たしてこの作品の受け止め方は如何なるものか。
観る人の居住地もしくは出身地によって評価や反応が微妙に変わる、そんな作品なのかもしれぬ。
|

|
|

|
|
|
2019.02.26:失われた建物に纏わる小さな記録
|
|
|
|
江別市立江別第三小学校
旧所在地:北海道江別市緑町西一丁目37
江別駅に降り立ち、「本町通」と呼ばれる駅前通りを暫し西北西に進む。
その道路と交差する「札幌江別通」を越え、通りの名称が「公園通」に変わって更に一ブロック。
そこから左手に伸びる道路沿いに視線を移すと、当該小学校の円形校舎が見える。
その第一印象は、坂本鹿名夫の設計でありながら、同じく氏によって定式化され国内に多数建てられた他の円形校舎とはやや異なる風情といったところ。
まずキャンチスラブが外周に廻らない。
そしてそれが故に目立つ帳壁の腰部分が煉瓦積みとなっている。
イギリス積みを基本としたその煉瓦造の外壁は、既存校舎に合わせたものなのであろう。
と同時に、その既存校舎も含めて統一された外壁が、敷地の接道面に植えられた高木や地被の緑と心地良いコントラストを醸す。
 学校建築としての合理性の追及に主眼が置かれ、ために特殊化し地域から切り離される異形性。
それが却って地域の象徴性を獲得するという逆説。
一時期興隆した円形校舎に対しては、この様な印象を持っていた。
学校建築としての合理性の追及に主眼が置かれ、ために特殊化し地域から切り離される異形性。
それが却って地域の象徴性を獲得するという逆説。
一時期興隆した円形校舎に対しては、この様な印象を持っていた。
しかし当該事例は異なる。
定型に則りつつも煉瓦の産地という特性をその表層に纏うことで帯びる地域性。
当該小学校のサイトにアクセスしてみると、この円形校舎に対する深い愛着と誇りがページ上に溢れていた。
そして外観目視においても、メンテナンスが行き届いているという印象。
だから、この校舎は末永く供用され続けるものだと勝手に思い込んでいた。
従って、統廃合とそれに伴う校舎建て替えのニュースをTVの報道番組で知った際には少々驚くこととなった。
少子化という人口構造の推移に対し、学校建築がその存在を継続し得る力は極めて弱い。
報道の中で、閉校前に見学会が開催される旨も紹介されたので早速赴いた時のことはこの場にも2015年5月7日に書いた。
建て替えられた新校舎については、ネット上でその画像を確認するに留まっている。
そこに写る外観は、塔屋の南東側立面に円弧を導入することでかつての円形校舎の名残を辛うじて継承しようと試みた様にも読み取れる。
|

|
|

|
|
|
2019.02.17:丸大雑記
|
※1:
 旧丸大長岡店店舗南側立面。
旧丸大長岡店店舗南側立面。
外壁色は改められているが、それ以外は概ね旧態を維持している。

※2:
他にも旧大和デパートが現存し、屋内もフロアは限られるものの他用途に転用され継続活用に供している。
しかしその外観は私が在住していた頃からは大幅に改められているし、既に再開発事業による建替計画が持ち上がっている。
それ以外の三店舗は除却済み。
更に駅の東側にも旧ダイエーの店舗建物が現存。
こうして書き連ねると、同市駅前のかつての商業地としての興隆が偲ばれる。
|
|
|
かつて私が過ごした街、新潟県長岡市の駅前に建つイトーヨーカドー丸大長岡店が閉店したということを、市内在住の方々のblogで知る。
当該商業施設の開業は私が長岡を離れたあと。
blog掲載の内観画像を見て初めて「内部ってこんなになっていたんだ」などと思うくらいだから、馴染みは薄い。
一方、拝読したblogの中には当該商業施設の設計者についての言及がなされているものもある。
開業の経緯について詳しい御様子なので、機会あらば色々と語って貰えないものだろうかと少し関心を持つ。
ここをお読み頂いている人の中には、その店舗名に違和を持つ方もいらっしゃると思う。
「イトーヨーカドー」はともかくとして、その後ろにくっつく「丸大」って一体何だということになろう。
あるいはその名称から、地元で古くから小売業を展開していた「丸大」という企業がイトーヨーカドーと業務提携した経緯を読み解かれる方も多いのではないか。
実際、今回閉店する駅前の建物がオープンした1988年以前は、同じ駅前商業地の一画で独自の大規模小売店舗を構え営業を行っていた。
その開業は1962年。
駅前通りに面して建てられた店舗※1は未だ現存。
しかもその外観は概ね旧態を遺す。
更には、用途が「長岡市民センター」という行政施設に変わったとはいえ屋内も活用され続けている。
私の在住時、駅の西側商業エリアに連なっていた五つのデパート(在住時だから、イトーヨーカドー丸大長岡店は除く)の中で、そんな建物はこの旧丸大の店舗だけとなってしまった※2。
その内外観には興味をひくものを何ら見い出せぬ。
しかし今となっては、かつて長岡市民であった者にとってとても貴重な物理存在ということになる。
9年前、既に長岡市民センターに転用され供用が始まっていた当該旧店舗を訪ねた際に、たまたま未利用の地下一階が公開されていた。
活用方法の提案受付もしくはテナント募集を目的とした公開だったのだろう。
かつて丸大の百貨店として供用されていた頃、そこは食料品売り場だったろうか。
当然のことながらその面影が一切取り払われたガランドウの「デパ地下」は、それはそれでちょっと新鮮ではありましたか。
 旧丸大長岡店地階フロア
旧丸大長岡店地階フロア
|
|
 旧丸大長岡店屋内階段
旧丸大長岡店屋内階段
|
あるいはその際確認した建物南西隅角部に配置されている屋内階段の手摺は、骨太のフレームにオレンジ色のアクリルパネルを嵌め込んだもの。
恐らく旧態のままの筈だ。
朧げな記憶の中に留まる意匠の現存は、ここのみならず様々な箇所に見受けられる。
勿論、耐震補強等、現在の建物に求められる性能を満たすための工事は施されているものの、外観同様に内観も旧態を良く遺す。
これは、限られた予算のもとに転用を図るために最小限の改修に留められた結果なのであろう。
さて、今般閉店したイトーヨーカドー丸大長岡店の方は、これからどのような活用が図られるのか。
地元企業数社が共同で建物を取得したと聞くが、今までと同様の商業施設として存続させるのか、それとも大胆な転用が図られるのか、あるいは周辺一体と共に再開発事業が策定されるのか。
元市民としては気になるところだ。
|

|
|

|
|
|
2019.02.10:【書籍】「自然」という幻想
|
|
|
|
新建築1月号の建築論壇は、乾久美子による「えき・まち、その公共性の未来」。
エマ・マリス著の『「自然」という幻想』の引用に端を発し、「自然とは何か」という問いかけから「そもそもまちとは何か?」という思索に繋げ、更には同号に掲載される氏の作品「延岡駅周辺整備プロジェクト」という具体事例の計画プロセスに関する解説へと展開するその内容はとても興味深い。
『「自然」という幻想』は未読だったので、これを機に読んでみた。
書籍のサブタイトルには、「多自然ガーデニングによる新しい自然保護」とある。
その表記の通り、自然保護をテーマとしている訳だが、この手の書籍は変な洗脳を受けぬ様に注意しなければという取り敢えずの警戒心をもって接することとなる。
しかし、書かれている内容は面白い。
自然保護の根幹である「自然の元来の姿」を取り戻そうとする活動が、その目的を見誤ることで陥る本末転倒もしくは愚かしい行為に対する批判。
そしてそういった原理主義に囚われぬ新たな自然保護の在り方の具体的な提示。
読み進めるうちに、「元来の姿」という問題は自然保護に限らず建築の保全にも当て嵌ることなのだと想いを馳せることになる。
歴史的建造物の復元に関しては、オーセンティシティという問題が常に絡む。
対象とする建物の「元来の姿」について、どの時点まで遡り、あるいは何を残し、そして保全しようとするのか。
そのことに対してより厳格であろうとすることは学術的にはとても重要だ。
けれども厳格であればある程、建築が今現在の社会において備えるべき要求性能や機能との距離は広がる。
そんな乖離と対峙する際、果たしてそれらを「建築」として視認し得るのか。
建築は「使ってナンボ」のものとする立場をとるならば、「かつて建築であった“モノ”」という価値判断に留まることとなる。
だから、むしろアダプティブユースに関心が向く。
一方、個人的に興味を持っている昭和40年代から50年代にかけて発売されたハウスメーカーの規格住宅の建築事例に対しては、より高いオーセンティシティを嗜好する傾向を自覚している。
つまり、建築の「元来の姿」についての考え方や好みも、自身の中で揺らぎがあるということになろうか。
あるいはそれは、対象を建築としてみるか歴史の一部としてみるかの差異でもあろう。
話を元に戻す。
環境問題に関わる対策として一般的に「緩和策」と「適応策」の二種が検討される。
緩和策は、環境の変動の進行を抑制することや変動の要因自体の削減。
適応策は、変動によって生じる様々な事象への対処をそれぞれ目的とする。
多くの場合両者は相補の関係に置かれるし、あるいは図らずもそれぞれの施策の立ち位置が入れ替わることも想定されよう。
個々の状況に応じ二種の対策をバランスさせ適切に対処することが求められる。
本書で批判の対象とされた事々は、極端な「緩和策」に偏向した状況ということになろうか。
この「緩和策」と「適応策」という分類は、まちづくり(都市再生)にも当て嵌められそうだ。
冒頭に記した「延岡駅周辺整備プロジェクト」は、衰退する駅前エリアに対する「適応策」の側面が強いのだろう。
けれども、経年において「緩和策」としての効果の顕然が期待されるのかも知れぬ。
各地で展開する再開発事業のプロセスやその後の推移について、この二つの視点から眺めてみるのも面白そうだ。
|

|
|

|
|
|
2019.02.04::メーカー住宅私考_101
|
※1:
資料によると、1984年1月時点で四箇所の総合住宅展示場及び当時新宿に在った同社単独展示場に、ミサワホーム555のモデルハウスが設営されていた。

※2:
タイプ名称に用いられた数字は延床面積の坪数を示したもの。
「54タイプ」は約54坪。
他のプランバリエーションとして、「51タイプ」「64タイプ」「68タイプ」が用意された。

※3:

販売資料等に用いられたミサワホーム555の外観写真。
1981年に開催された第14回東京国際見本市に出展されたプロトタイプモデル。
型式は、今回訪ねた事例とは異なる「64タイプ」。
|
|
|
昭和50年代にミサワホームが発表した企画住宅に関し、私はその殆どについて実物を観る機会を得ている。
建築事例の外観を確認するのみに留まるものもあるが、個々のモデルが販売されていた当時、住宅展示場や分譲物件等を通して内観を拝む機会を得たものも多数。
しかしその中で、「ミサワホーム555」と名付けられたモデルだけは内外共に未見。
その実在がずっと謎のままであった。
このモデルについては、「住宅メーカの住宅」のページの「不可解なモデル」の項でも言及している。
そちらの冒頭に書いた通り、商品名が目まぐるしく変化した。
ここでは取り敢えず1981年にプロトタイプとして公表された際のモデル名称を用いるが、正式発売後の推移を追ってみるとその販売期間は1982年4月28日に始まって少なくとも1988年頃まで継続している。
つまりはそれなりの受注実績があったということなのかもしれぬ。
けれども今迄その建設事例に関する情報を得るには至らず。
かのミサワホームG型でさえ近年になって数件の実在情報を得られたことを鑑みると異例だ。
あるいはもしかするとモデルハウス※1以外に実際に人が住む家として建てられたケースが無かったのではないかとさえ疑っていた。
しかし最近、中古住宅販売サイトで偶然その事例に出会うこととなった。
売り出されていたのは、延床面積に応じて4種類設定されたプランバリエーションのうち「54タイプ」※2と呼ばれていたもの。
掲載画像を見る限りでは、竣工時の姿を良好に保持している様だ。
これは観に行かねばということで、所在地である広島に向かった。
最寄駅から歩くこと二十分余。
その道程が殆ど登り坂なのは、目的地が丘陵を切り拓いて造成された住宅地であるため。
計画的に区画された広大な街区に建ち並ぶ戸建住宅群は、建築年代が昭和40年代半ば頃と思しきものから最近のものまで様々。
 そんな街並みの一画に、三階建てのボリュームを有するその建物は異彩を放って忽然と屹立していた。
否、右の画像の通り、隣に同社が1990年に発売した同じくユニット工法を用いた「NEAT EMBLEM」が建っていることによってやや違和は和らいでいる。
とはいえ「NEAT EMBLEM」はある程度住宅らしさを纏った外観。
やはり「ミサワホーム555」のそれは際立っている。
約八年の発売時期の違いが、同社のユニット工法における意匠性と生産性のバランスに変化と進化をもたらしたといったところか。
そんな街並みの一画に、三階建てのボリュームを有するその建物は異彩を放って忽然と屹立していた。
否、右の画像の通り、隣に同社が1990年に発売した同じくユニット工法を用いた「NEAT EMBLEM」が建っていることによってやや違和は和らいでいる。
とはいえ「NEAT EMBLEM」はある程度住宅らしさを纏った外観。
やはり「ミサワホーム555」のそれは際立っている。
約八年の発売時期の違いが、同社のユニット工法における意匠性と生産性のバランスに変化と進化をもたらしたといったところか。
目の前に建つ「ミサワホーム555」の現況は空き家。
しかも中古住宅として販売中なのだから、現地確認ということで心おきなくその外観を眺める。
その南側外観を見上げた際の第一印象は、かつてパンフレット等の掲載写真※3を見た際に浮かんだ「住宅の化け物」という言葉ほどに酷いものではなかった。
しかしそれでも、あまり冴えたものとも思えぬ。
個々のディテールに意が払われていることは判るものの、それらの集合体としての全体像は、ユニット工法の様々な制約が足枷となって今一つこなれていないといったところ。
「NEAT EMBLEM」と比べれば、その差は明らか。
けれども、大らかな勾配屋根を従えた北側の外観はなかなか良かった。
また、雨水排水竪樋を外部に露出させない納まりや玄関ポーチライトの扱い等、画像では判らなかった詳細を視認することも出来た。
当日は内覧は行われていなかったので屋内を確認することは叶わなかったが、今迄全く観る機会を得られていなかった建築事例を眼前に視覚の享楽に授かること。
その意義については、少なくとも建築鑑賞を趣味とする方々であれば御理解頂けるところであろう。
「不可解なモデル」の項に載せた当該モデルのページも、今回の件を反芻した上で必要に応じ改訂を試みようと思う。
|

|
|

|
|
|
2019.01.29:失われた建物に纏わる小さな記録
|
興一ビル一階のショッピング一条内観。
かつては一条市場と呼ばれていた。

両端が公道に面する鰻の寝床状のボリュームを持つ建物中央を貫く通路を挟んで両側に店舗が並ぶ屋内市場の形式は旭川市に多く分布するが、札幌市内では珍しいかも知れぬ。
|
|
|
興一ビル:札幌市中央区南1条西10丁目
札幌の市内中心部を散策中、当該建物に目が留まったのは2011年8月。
南面のファサードは、ありふれた材料と少ない要素ながらもそれなりに意を払っているという印象。
しかし、隣地建物との僅かな離隔から目視可能な側面は、正面のそれとはまったく異なる様相。
等間隔に開口が穿たれた小波鋼板を張った壁面に鋼板葺き緩勾配の切妻屋根という、倉庫か工場の様な趣き。
正面のみを建物名称に負けぬようにそれなりに仕立てた外観は、「看板建築」にカテゴライズされることとなるのだろうか。
それは、この建物が建設された1950年代初頭において、周囲に次々と建てられ始めていたオフィスビルや商業施設を参照し、あるいはそれらに対抗する意図を持って構想されたものなのかも知れぬ。
都市への面白い納まり方に、暫し道路の向かい側からその外観を愉しむ。
 南側立面
南側立面
|
|
 北側立面
北側立面
|
南側立面の二、三階は、網入り型板ガラスをパテ留めした二枚引き違いのスチールサッシを二行三列規則的に配置。
中桟と竪桟を塩梅よく割り付けることで、ほぼ正方形の開口ながらプロポーションは悪くない。
開口の上下にアルミパネルを張り付け、開口と共に両端に鋼製の細いマリオンを通してモルタル左官仕上げの方立て壁と縁を切る。
そんな上層部に対し、一階は中央に三連の出入口を配置。
両脇を濃紺の施釉タイルとガラスブロックでシンメトリーに固め、基壇を成す。
全体構成は意外と端正に纏まっている。
一階の三連の出入口のうち、向かって左手のものは上層階に到る階段室用のもの。
四方框にガラスを嵌めこんだ親子扉で、中央にステンレス製の横桟を三本平行に流して把手としている。
外壁に取り付く看板から、二階より上のフロアには喫茶店や事務所がテナントとして入居していることが確認出来る。
右手の出入口扉は、道路に直接面する一階店舗用のもの。
同じく親子扉で、左手のものとは開き勝手が左右逆となっている。
実見時点では中華料理屋が営まれていた。
そんな左右二つの出入口に挟まれた中央の両開き扉から屋内に入ると、建物の背後まで中廊下が一直線に伸びて裏手に面する中通りへと接続する。
中廊下の両脇には店舗の用途に供する区画が並ぶ「ショッピング一条」と名付けられた商業ゾーンを形成。
私が訪ねた時点では左の画像にある様に、壁で塞がれた区画が目立ち、営業を継続している店舗は限られていた。
中廊下の末端まで歩を進め、屋外に出て振り向くと目に飛び込む北側立面は、南側とは全く雰囲気が異なる。
二階、三階がどうなっているのかは確認していない。
恐らくは一階と同様に建物中央を共用廊下が貫き、その両脇に貸室が連なっていたのであろう。
しかし、確認しないうちに当該建物は除却されてしまった。
|

|
|

|
|
|
2019.01.21:戦後空間シンポジウム
|
|
|
|
「徘徊と日常」のページでも触れたが、1月14日に建築学会主催で開催された「戦後空間シンポジウム02:技術・政策・産業化 −1960 年代 住宅の現実と可能性−」を聴講した。
場所は東京港区の建築会館。
第二回と銘打っている通り、連続開催を予定しているシンポジウムで、年代を区切って様々な切り口から戦後の建築空間の在り姿を検証しようというもの。
で、第二段となる今回は1960年代。
この時代の住宅産業の動向とそれに纏わる政策がテーマ。
シンポジウムは、最初に識者二名からそれぞれのテーマについて講演が行われた。
まずは松村秀一東京大学特任教授による1960年代の住宅産業の動向について。
その内容や画面に映し出される画像は、個人的には殆ど既知のもの。
しかしそこは東大の教授(・・・だから必ずしもという訳では無いだろうが)、話が本当に上手だ。
判りやすく、しかもグイグイと聴衆を引き込むように講義が進められ、持ち時間の一時間で60年代の状況に関し話を纏め上げるその基調講演は聴き応え十分。
参加して良かったと満足出来る内容であった。
続いて、平山陽介神戸大学教授による政策面の話。
政策というと、例えば揺籃期にあった60年代の住宅産業を巡る建設省と通産省の壮絶な主導権争いの話が中心になるのかなと予想していたのだけれども全然違って、もっと深い内容。
新鮮だったのが、持ち家の所有に所帯を持つことへの誘導がセットとなっているという指摘。
そのセットこそが国民にとっての最大公約数の幸せという価値判断のもと政策が組み立てられ今日に至る住宅市況が推移した。
その取っ掛かりとしての60年代の状況についての詳述はとても興味深かった。
ふと、攻殻機動隊の原作の冒頭で語られた「貴国こそ脳は資本主義を名乗られるが、実際は理想的な社会主義だ。」というセリフを思い出す。
聴講者からの質問を募る時間があったので、私も松村氏に質問をしてみた。
氏の講演内容は、コンクリート系プレハブと軽量鉄骨系プレハブの動向を中心に組み立てられていた。
つまり、都市の不燃化の必要性から前者、鋼材の新たな市場開拓の必要性から後者の工法に纏わる技術開発が進められ、そこにベンチャー企業や異種産業が参入してきたという60年代の状況は理解出来る。
しかし、もう一つの工法として当時勃興し始めていた木質系プレハブのことが話から抜けていた。
それは話を組み立てる上で意図的に排除したものなのか、あるいは言及し得ぬ状況が60年代の木質プレハブの在りようだったのかといった興味からその点についてのコメントを求めてみた。
回答は十分に納得出来るものであった。
すなわち、木質系プレハブについても様々な事例が60年代に登場しつつ、70年代半ばの2×4工法のオープン化と共に極々一部を除き淘汰。
あるいは、前二者の技術開発プロセスが、業界団体もしくは行政主導の下に組織立った態勢が機能していたのに対し、木質系は企業単位の面が強かった。
従って、当時の技術の継承や蓄積が前二者に比べると弱く、今回のテーマの中では取り上げにくいとの指摘。
なるほど、木質系プレハブの動向が他二工法のそれとは少々勝手を異とする状況は、例えば北海道における60年代の状況を調べてみても同様ではある。
事業としての継続性や工法そのものの技術的妥当性に関して(言葉を選べば)結構ユニークな事例が、当時の資料において散見されぬ訳でもない。
地元工務店を中心としたそれらの事例の推移を追跡してみるのも面白そうだ。
それにしても、シンポジウムに参加した際の常であるが、パネラーの方々の頭の回転の速さにはいつも驚かされる。
あるいは、私はともかく他に発言された聴講者の方々の質問の内容もとっても高度なもの。
その知的な言説の応酬を暫し愉しむひと時となった。
|

|
|

|
|
|
2019.01.13::メーカー住宅私考_100
|
|
|
|
以前、知人が御自身のブログの中で、「人生を変えた10のデザイン」という連載を組まれていた。
それを読んで、私が影響を受けたデザインについて考えてみると、とても10項目は思い浮かばぬ。
しかし一つは迷うことなく即座に挙げられる。
それが、知人も掲げていたミサワホームO型。
1976年9月に発表されたこの規格型住宅のテレビコマーシャルを見た時の衝撃と以降の経緯については、八年前にこの場に連載した「住宅メーカー私史」でも述べている。
それこそ、今現在私が建築を生業とするに至ったきっかけは、幼少のみぎりに出会ったこのミサワホームO型に他ならぬ。
つまり、このモデルに出会うことが無ければ今の私はきっと存在しない。
あるいは、O型がこの世に発表されなければ今頃私は何をしていたのだろうとも思う。
それ程に私にとっては極めて影響の大きい存在であった。
その割には、同社とは全く関係の無い仕事に就いているのだけれども・・・。
ともあれ、そんな経緯からこのサイトの所々で幾度もこの住宅について言及している。
しかしこのモデルの魅力について余すことなく文章に出来ているとは全く思えていない。
それは、かつて内橋克人が出版した「続々続々匠の時代−ミサワホーム「木と家と人」物語」の冒頭で、同モデルについて実に的確且つ詩的に表現されているため。
外観に関する記述を少々引用してみる。
|
それを、のびやかで牧歌的な田園風景の中に立たせれば、深く濃い緑とよく似合う。
豊かに実った稲田の向こうに、まるで大屋根の土蔵か、庄屋の旧家のように、それは重くそそり立っている。
赤い実の柿が、黒白の陰影に刻まれた大屋根と壁の対比に映えて、水墨画のように浮き上がって見えるのだ。
また一方、整備された都会の、やや窮屈な住宅地であれば、モダンで瀟洒な個性の一面がにわかに自己主張を始め、それでいてユトリロの絵を思わせるような、奥深い静けさをかもし出してくる。
|
同書は既に廃刊。
しかしその内容は、昭和50年代を中心とした同社の商品開発の詳細が臨場感たっぷりに描かれたものであり、住宅史の一端として極めて高い資料的価値を有していると思う。
さて、空間構成や内外観デザインに関し深い感銘を受けたO型であるが、しかしプランについては同社から同時期に発表されたA型二階建てやSIII型の方により強い関心を持った。
それぞれのプランについても、このサイトの所々で幾度か取り上げているので繰り返さない。
しかし、この2モデルを見知った小学校高学年から中学生にかけての時期は、自分なりにこれらのプランを応用してより良い間取りが創り出せないかと随分試行を愉しんだものだった。
無論、それ以上の物など出来る筈も無い程に、二つのモデルは完璧なものであった。
そして近年になって、更に往時のモデルの中でハウス55の第8号居住実験棟やM型2リビングの間取りが評価の対象として加わる。
これらの優れた間取りに接し、眺め、愛でている時間というのは個人的には至福の極み。
残念ながら、最近のハウスメーカーのプランで同様の気分を堪能できる事例にお目にかかることは、極めて稀だ。
|

|
|

|
|
|
2019.01.06:鳴門市文化会館
|
|
|
|
今年の年賀状に用いた画像の元ネタは、増田友也設計の鳴門市文化会館。
そのホワイエの壁面に穿たれた開口廻りになる。
 居住地が関東であるがために同建物を訪ねることは個人的には非日常の体験に属することとなるが、私は今のところ三回訪ねている。
居住地が関東であるがために同建物を訪ねることは個人的には非日常の体験に属することとなるが、私は今のところ三回訪ねている。
初回は真夏の炎天下。
強烈な南国の日差しを浴びて光と影の中にくっきりと浮かび上がる怒涛の造形群に畏怖の念を抱きつつ、時間が経つのも忘れて建物周囲を巡っておりましたか。
二回目は、曇天模様の冬日。
陰鬱な空の下、初回の印象とは全く異なるコンクリート剥き出しのボリュームが織りなす佇まいと暫し対峙したことはこの場にも以前書いた。
そして三回目は昨年の秋。
快晴の心地良い天候に恵まれつつ建物鑑賞を存分に愉しむことが出来た。
遠隔地の建物を幾度も観に行くことなどそんなに多いことではない。
しかし鳴門市文化会館は、そんな気にさせる魅力を有する作品だ。
特に三回目に関しては、昨年の6月から7月にかけて徳島新聞に連載された「保存か解体か−鳴門にのこる増田建築」という記事を読んで改めて訪ねてみたいという気になった。
ネット上に公開されている16回に及ぶ同連載にて初めて、増田友也という建築家の人となりを知ることとなった。
その作品のみならず、プライベートまで含めた人物像にも焦点をあてた記事はとても興味深い。
中でも遺作となった鳴門市文化会館への取り組みに関する記述は鬼気迫るものがある。
なるほどこの様な経緯があっての同作品かと思うと、建物に注ぐ視線もまた変わることとなる。
三回目の訪問時には内観も拝む機会を得た。
年賀状掲載画像はその際に撮ったものになる。
|