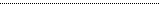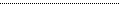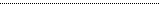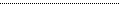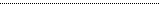|
|
2009.03.28:建築と船舶
|
※1:
会期:
2007年3月3日〜9月2日
主催:
日本郵船歴史博物館

※2:
 日本郵船歴史博物館(旧横浜郵船ビル)外観
日本郵船歴史博物館(旧横浜郵船ビル)外観
|
|
|
建築と鉄道について1月10日の雑記に書いた。
その流れで、もう一つ。
二年前に、横浜市の日本郵船歴史博物館で、「洋上のインテリア展」が開催された※1。
サブタイトルに、「船内装飾と建築にみる近代日本デザイン」と謳い、建築家が手がけた豪華客船のインテリアや日本郵船ゆかりの建築を扱った興味深い企画展。
戦前の豪華客船は、「国土の延長」として国家の威信を表徴させる意識のもと、その内装設計が行われたという。
陸上の建築とは異なる制約の中、海外の技術導入から始まった様々な取組みは、前川國男や村野藤吾等の著名国内建築家の起用によって「新日本様式」と呼ばれるまでに洗練された。
展示会場である「日本郵船歴史博物館」の旧名称は横浜郵船ビル。
1936年竣工。
約50mにわたって16本のコリント式の柱が並ぶファサードが圧巻※2。
東京丸の内に1923年に竣工した旧日本郵船ビルは、老朽化を理由とした建替えのために、1976年に取り壊されて跡形も無い。
建替え後の新しい建物の足元に、旧建物の外壁につけられていたと思われるテラコッタ製の装飾がオブジェとして置かれるのみ。
個人的には、小樽支店が気に入っている。
重くて暗い印象もあるが、北の風情に合っている。
金唐皮紙を用いた内装の荘厳さは、他の歴史的建造物の内装のそれを十分に凌ぐ奥ゆかしさを醸している。
寒地建築としての防寒対策の工夫も面白い。
|

|
|

|
|
|
2009.03.20:土曜夜間講座
|
|
|
|
大田区にある昭和の暮らし博物館で、今年も「土曜夜間講座−火鉢を囲んで建築の歴史」が始まった。
現在の居住地からは少々離れているが、気合を入れて参加。
この講座に出席するのは二年ぶり。
昨年は、テーマのマンネリを感じたのとモチベーションの減退があって参加しなかったのだ。
今年はいずれの講義も面白そうなテーマだったので、全て申し込む。
初回3月7日のテーマは、「近代化遺産を歩く」。
写真家・増田彰久氏が、御自身撮影の近代化遺産について解説する講座。
その内容は、煙突や橋梁、通信塔、トンネル等々、極めて広範囲。
初見のものが多数あり、とても面白かった。
中には、修景と称して対象物やその周辺が過度に整備されてしまった事例も見受けられた。
つまりは、電線や電柱の類を地中化し、路面にインターロッキングブロックを敷き込み、ガードレールを擬木製にする等々の措置。
綺麗に整えられたその場所は、堆積してきた時間の重みがすっかり清算されてしまい、残されたのはテーマパーク的なフェイクへと堕した風景。
本物を模倣したテーマパークを、本物自体が模倣するパラドックス。
修景は、その匙加減が本当に難しい。
講義の最後に、「近代化遺産は、それぞれの生活圏内に人知れず存在する」といった旨の発言があった。
近代化遺産に限らず、何気ない日常風景の中に素晴らしい価値を見い出す眼。
そんな意識のもと、改めて自らの周囲に目を向けてみたいと思う。
3月14日は、「日本建築の基礎知識」
講師は、国立歴史民俗博物館教授・玉井哲雄氏。
配布されたレジメには、既知の単語が並ぶ。
しかし、いざ話が始まると初めて知る内容が一杯。
その一つ一つに対する丁寧かつ判りやすい説明に好感が持てた。
中でも、神社と御神輿の関係についての話は興味深かった。
昨年6月21日の雑記に、浦安三社祭で観た御神輿に設置されている装飾の鳥居が、いずれも明神系で神明系のものが無いことへの疑問というか興味を持った旨を書いた。
その理由が判りかけた様な気がする。
但し、もう少し自分で調べてみる必要がありそうだ。
今年の「火鉢を囲んで〜」の講座は、残りあと二回。
いずれも興味深いテーマなので楽しみだ。
|

|
|

|
|
|
2009.03.14:再開発雑感
|
※1:
 1929年竣工の三井本館(左側)と、2005年竣工の日本橋三井タワー。
1929年竣工の三井本館(左側)と、2005年竣工の日本橋三井タワー。
日本橋三井タワーの低層部は、大オーダーの列柱の上に二段の屋階が載る三井本館の構成を、現代建築のディテールを用いつつ巧みに踏襲している。
高層部分のカーテンウォールも、優美で繊細。
 ※2:
この界隈における、江戸時代から続く三井の歴史については、鈴木博之著の「建築の遺伝子」に詳述されている。
土地と建物に纏わり連綿と生成される都市の現象としてとても興味深い。
※2:
この界隈における、江戸時代から続く三井の歴史については、鈴木博之著の「建築の遺伝子」に詳述されている。
土地と建物に纏わり連綿と生成される都市の現象としてとても興味深い。
 ※3:
その発言の中身は、この建物の優れた点に関する具体的な言及が乏しい。
煉瓦造とか石造のクラシカルな建物は、建築への興味が薄い人でも文化的な価値を共有し易い。
しかし、東京中央郵便局の様に、一歩間違えれば凡庸な四角い箱に堕するギリギリのところで「作品」として成立している場合は微妙だ。
実際、少なくともネット上では、その価値判断は相半ばしている印象。
※3:
その発言の中身は、この建物の優れた点に関する具体的な言及が乏しい。
煉瓦造とか石造のクラシカルな建物は、建築への興味が薄い人でも文化的な価値を共有し易い。
しかし、東京中央郵便局の様に、一歩間違えれば凡庸な四角い箱に堕するギリギリのところで「作品」として成立している場合は微妙だ。
実際、少なくともネット上では、その価値判断は相半ばしている印象。
文化的側面の言及は現在の所管ではないのだろう。
しかしここはひとつ、この建築の魅力を御自身の言葉で大いに語ってもらいたいものだ。
|
|
|
日本橋三井タワーの見学会があり参加した。
この超高層ビルは、建築物総合環境性能評価システム"CASBEE(キャスビー)"の認証制度で、最高ランクの「S」を取得している。
その環境配慮技術の御披露目が見学会の趣旨。
設備関連の環境負荷低減技術が主であったため、専門外の私には今ひとつピンとこない面もあった。
しかし、低層部分の巨大吹抜け空間を効率的且つ快適に空調する手法や、エレベーターシャフトのドラフト対策等は興味深かった。
結果として、PAL値190.5MJ/平米を実現されている。
この日本橋三井タワーに隣接して、重要文化財に指定されている三井本館が鎮座する※1。
ここでも、歴史的建造物の保全に絡む容積率の上乗せで、超高層棟の建設が実現した※2。
既にこの場で何度か書いている通り、東京駅前に広がる丸の内エリアも、同様の法的手法を駆使して歴史的建造物と超高層の組合せが幾つか実現している。
かつての絶対高さ制限100尺の歴史を前向きに捉えた再開発によってもたらされる日本独自の超高層建築形態である点で、興味深い事例がここ数年の間に一気に実現した。
とはいっても、興味深いこととデザイン的に優れていることとは別次元。
歴史と現在の相克の中で、なかなかに厳しい現実が顕然している。
そんな丸の内地区に比して、日本橋三井タワーのデザイン的な洗練度はずば抜けていると思う。
現代建築の枠組みを堅持しつつ、実に巧みに三井本館との調和を実現している。
道路を挟んで対面する街区でも、同じ三井不動産による「室町東地区開発」が始まっている。
そこに建設予定の建物の低層部は、日本橋三井タワーの低層部のイメージを踏襲する様だ。
一定のルール以外は個々の敷地内で完結したデザインが連なってしまっている丸の内とは異なり、景観的に整った街区が実現されそうだ。
ところで、丸の内の一角にある東京中央郵便局の再開発が揺れている。
既に報道にある通り、鳩山総務相の発言が発端だ※3。
そこに政治的意図がどの程度含まれているのか、あるいはその意図が如何なるものかは測りかねる。
しかし、近代建築の文化的価値や保存と再開発の問題に対して広い関心を集めるならば、それはそれで意義はあろう。
実際、鳩山発言以降、例えば3月12日の読売新聞には「保存建築 まるで接ぎ木」と題したこの地域の再開発事業に対する記事が大々的に載せられたし、ネット上でもこの建物を巡る文化的価値に対する議論が活発化した。
そして、保存部分の拡大と登録有形文化財への登録申請も決まった。
僅かな前進と言えるのだろう。
しかし、不勉強なのでよく判らないが、三割程度の部分保存で、登録有形文化財への登録対象となり得るのだろうか。
文化財に資する事物の保全拡大を目的とした比較的緩い制度であるとの認識は持っているが、しかしこれが可能なら、登録を免罪符とした申し訳程度の部分保存による再開発が今後増えるかもしれない。
|

|
|

|
|
|
2009.03.07:ビッグバンから
|
|
|
|
建築家大沢匠氏の鎌倉のアトリエで、同じく建築家の黒沢隆氏による日本の住宅をテーマにした講義が催され、出席した。
開催は、平日の午後7時。
都心勤務ゆえに移動時間を考えるとなかなか辛い時間設定ではあるが、自分にとって何が大切か考えるまでもない。
仕事を強引に断ち切って、鎌倉に馳せ参じる。
黒沢氏といえば、思い浮かぶのが「個室群住居」。
60年代後半に提唱されたその概念について、同名の著書も出版されている。
家族や個人の本質から住居のあり方を模索した内容だが、なぜか前半は猿の進化や生態の話が延々と続く。
読む側は、「これって住居に関する本だよな?」と訝しがりつつ読み進めることになる。
でも、読み終えて納得。
本来、住まいを考える上で、「家族とは」との問いかけは、「ヒトとは」「生命とは」という次元にまで関わるべき問題なのだ。
そこに真摯に取り組み続ける建築家として、黒沢氏の右に出る人はいないかもしれぬ。
今回の講義もそうであった。
まさか、日本の住宅史をテーマとした講義で、ビッグバンから話が始まるとは想像だにしなかった。
宇宙創生から生命の進化を経て、古代の世界史を展開しつつ「日本とは」「日本人とは」という問題に迫りながら、縄文期の住居形式まで話を進める。
その間、きっかり90分。
大学での講義歴が長いため、意識しなくても一回の話が90分になるよう体内時計が仕組まれてしまっていると、御本人も笑いながら仰っていたが、実に見事な講義であった。
今回話した内容の参考になる書籍として、御自身の蔵書を何冊かお持ちいただいていた。
建築学よりも、むしろ人類学に関する書籍の方が多い。
建築家としての広範な知識の収集姿勢に感心する。
今後も連続講座に出来ないかとのお話があったが、具体的なスケジュールは未定。
実現するならば、どんな展開になるのか楽しみだ。
|

|
|

|
|
|
2009.02.28:CO2削減
|
※1:
 中央奥に、新宿副都心に建設途上の都庁舎。
手前右側が新宿野村ビル、左側が新宿センタービル。
中央奥に、新宿副都心に建設途上の都庁舎。
手前右側が新宿野村ビル、左側が新宿センタービル。
1990年の夏頃に撮った様に記憶している。
当時は、建物の修繕や改修の手法まで含めた各種検討を行う意識は希薄だった。
実際、建物の外装が出来上がりつつあったこの時期に、マスコミを中心に巻き起こっていた議論は「豪華批判」などのあまり建設的とはいえぬモノばかりであった。
そして、まさか十数年後、建物保全のためにこれだけの莫大な費用が計上されるとか、その際にCO2削減量を提示する世の中になるとは、往時は誰も予測し得なかっただろう。
|
|
|
東京都が、来年度から10年間にわたって本庁舎の改修工事を行う旨、発表した。
建物の適切な保全を考えるならば、築後18年も経てば大規模修繕は必要であろう。
定期的なものも含めて、今までどのようなメンテナンスを実施してきたのかは知らない。
しかし抜本的な修繕が今回が初めてだとするならば、むしろ少々遅かったと言えるのかもしれない。
ネット上では、報道機関から個人のブログまで含めて、批判的なニュアンスの意見が早速載せられている。
確かに、約780億にも及ぶ改修費用額については、様々な意見があって然るべきだ。
しかし批判する人達も、あらゆる建物がメンテナンスフリーでは有り得ないことは承知していよう。
公共建築に関わる工事や改修について、マスコミ等で金額のみが喧伝され独り歩きするのはいつものことだ。
いい加減な報道姿勢に乗せられるのではなく、建物そのものの評価や、長期修繕計画がどのように策定され実行されてきたのかを含め、その妥当性が判断されるべきだ。
今回の大規模修繕では、設備機器の更新による省エネ化を進めるて二酸化炭素の排出量を年間約2400トン削減する目標を掲げている。
私は、この部分には違和感を持つ。
環境負荷低減の御旗のもと、CO2排出削減量の提示が何らかの事業行為を推進する際のクリシェと化している気がしてならない。
そして、この削減量の算出根拠は一体何なのだろうとも思う。
今のところ、東京都公表の資料に根拠と思しき記述は見当たらない。
果たしてライフサイクルまで鑑みた削減量なのか、それとも改修後の供用に限定した削減量なのか。
それに、冷房や暖房に用いる空調機器の性能(COP値)をいくつに設定するかでその算出値も大きく変わる。
ということで、今回の都庁舎の件に限らず、指針や基準、根拠が今ひとつ曖昧との印象を持つCO2削減事情ではある。
そしてそれ以前に、環境負荷とCO2排出量の因果関係という「そもそも論」も重要であろう。
しかし、環境とCO2を漠然と一体の関係で捉える考え方が一般化しているのも事実。
であるならば、排出削減量の算出に関し、明快な根拠や評価手法の整備が必要なのではないか。
|

|
|

|
|
|
2009.02.21:丸の内雑感_3
|
|
|
|
東京駅前に建つ東京中央郵便局の外壁の一部に足場が組まれてパネルで覆われた。
外観デザインのポイントとなっていた大時計も、時針と分針が取り外されて数字のみとなっていた。
敷地境界の仮囲いには「解体工事のお知らせ」が既に掲げられている。
いよいよ除却工事着手かと思ったが、2月12日付けの読売新聞の記事によると、現在構造関連の調査中とのこと。
いずれにせよ、再開発に向けた行政手続は着々と進行しているようだ。
その東京中央郵便局の近くで施工中の丸の内パークビルディングは、完成形が徐々に見えてきた。
しかし、それと同時になかなか苦しい印象の部分も見えてくる。
例えば写真1。
三菱一号館の南面を馬場先門に向かって撮ったものである。
手前に、復元工事が進む三菱一号館。
その左隣に、施工中の丸の内パークビルディングの低層棟。
更にその先に超高層の明治安田生命ビルが立ちはだかり、一番左端に重要文化財に指定されている明治生命館が見える。
様式もボリュームも異なる建物が建ち並ぶ景観が形成されている。
とりわけ丸の内パークビルディングの低層棟は、何とも微妙な存在だ。
別に、統一感の無い景観は日本では極々普通であり特筆することでもない。
しかし、写真1左手の明治安田生命ビルの低層部分と明治生命館が、辛うじて歴史的連続性の有る街区を作り上げていただけに、この混乱は何とも惜しい。

写真1:
|
|

写真2:
|
写真2は、丸の内パークビルディングの東側低層部分を撮ったもの。
手前に三菱一号館が見えるが、その右側のガラス面の基壇にクラシカルな石積みを視認していただけるだろう。
その右端に白い塔の突出も確認できる。
これらは、かつてこの場所に建っていた「丸の内八重洲ビルヂング」の断片だ。
いわゆる「かたぶた保存」に該当しようか。
脱皮して際限なく肥大化した物体が、抜け殻の残骸を足元に付着させているかの如き印象だ。
超高層棟に飲み込まれるようなその断片のあまりにも儚げな存在感が何とも痛々しい。
可能な限り忠実に再現された三菱一号館に隣接していると、なおさらである。
改めて観てみると、丸の内パークビルディングは要素が一杯だ。
歴史的建造物の忠実な再現と、かさぶた保存。
超高層棟と、微妙な存在の低層棟。
周囲との関係も含め、果たして後世においてこの街区の再開発がどのように評価されるのか、少々興味を持つ。
|

|
|

|
|
|
2009.02.14:間取りを巡って
|
※1:
 間取り逍遥のページに掲載している物件No.02の元ネタとなった折込みチラシの一部分が上記。
間取り逍遥のページに掲載している物件No.02の元ネタとなった折込みチラシの一部分が上記。
本当は、この様に直接広告の図面を載せた方が、リアルで良いのかもしれない。
ちなみに、表示されている販売価格は1550万円。
都心からさほど離れていないところでも、築年数がある程度経過したものであったり、駅から離れていたりすると、このような事例もある。
|
|
|
2月9日に、「間取り逍遥」というページを新たに設けた。
八番目のメインコンテンツである。
私は住宅の間取りを見たり考えたりすることが大好きだ。
別にこれは特異な趣味ではない。
住宅間取り図マニアに対して「間取りスト」とか「間取ラー」等の呼称もあるくらいだ。
そこまでの領域には達していないにしても、しかし私の場合も、新聞に入ってくる不動産関連のチラシの中に琴線に触れる間取りを発見しようものなら、一日中眺めていても飽きない。
間取りから実際の空間を想像してみたり、設計者の意図を考えてみたり、あるいは自分であればこの様に設計するだろう等々、間取り図を前に延々と想いを巡らせるのだ。
だから、間取り図を「見る」というよりは「読む」、あるいは、その図面の中を「逍遥する」といった方が良い。
そんな過程の一端を書き連ねてみようというのが、当ページの命名意図だ。
作成にあたって少し悩んだのが、間取り図の掲載方法。
基本的には、新聞の折込広告等に掲載された間取りで琴線に触れた事例を扱うが、広告をそのままスキャンして載せる訳にはいくまい※1。
広告によって図面の表現がバラバラだから、各ページの統一感も出せなくなる。
さりとてトレースも手間といえば手間だ。
しかし、なるべく表現を簡略化してトレースすることにした。
トレースによって見えてくる間取りの特質もあろう。
更に、自分なりに個々の間取りの改善案を提示する場合もあるだろうから、CADデータ化しておいた方が便利だ。
こんな経緯から、まさか宅建業法に抵触はしないだろうけれども、「図面と実際が異なる場合は、現物を優先します」と、不動産広告お定まりの注意書きを半ば冗談で添えさせて頂きましょうか。
とりあえず、集合住宅三件を載せた。
戸建住宅についても掲載する予定だし、新築だけでなく中古も取り上げてみたいと思う。
目下、ネタの洗い出し中だが、昔の住宅の方が面白い間取りが多いような気がするのは、単に個人的な嗜好だろうか。
|

|
|

|
|
|
2009.02.07:歌舞伎座
|
※1:
 歌舞伎座の外観・・・といっても、これは裏側。
歌舞伎座の外観・・・といっても、これは裏側。
個性的な正面側の意匠とはまるで異なる、文字通りの裏側だ。
天端の軒瓦が、歌舞伎座らしさとして辛うじて視認出来ようか。
「建築の側面」のページのネタになるかなと思って撮ったものだが、特徴を説明する能書きも思い浮かばず、一年近く放置状態の画像。
気が向いたらそちらの方に載せてみたいと思うが、とりあえず、こんなアングルの写真を撮る人は滅多にいないだろうなということで、今回の機会に載せてみた次第。
ちなみに正面の外観写真は撮ったことが無いし、改めて撮る気も無い。

※2:
実際、1921年に漏電による火災で焼失。その後、焼失前の和風のイメージを踏襲した鉄筋コンクリート造により再建された。
更に1945年に戦災を受けている。
|
|
|
銀座に建つ歌舞伎座※1の老朽化に伴う再開発案が、1月28日に公表された。
かつて、近傍に木製サッシメーカー「キマド」のショールームが立地していた。
私的によく通っていたので、そのたびにこの建物を拝んでいたが、あまり良い印象は持っていない。
コンクリート造で桃山様式風の意匠を再現した外観は、建築史的には興味深い位置付けとなり得るのだろう。
なるほど、コンクリートの持つ可塑性ゆえの自由な造形が、伝統芸能を演じる場としての和の意匠を実現しつつ、劇場建築としての耐火※2等々の諸性能をも満たすための最適解だったのかもしれない。
しかし、自由な造形と擬態は別次元。
本来、木造であるべきディテールをコンクリートで擬態したその表層は、キッチュにしか見えない。
再開発で新たに作り出される意匠は、現況のシルエットを踏襲しつつも、かなりシンプルなデザインになる模様。
踏襲されたシルエットの背後には超高層ビルが屹立する。
既存建物のイメージ保存と超高層棟とのパッケージングは前例が幾つもあり、お定まりの再開発形式の一つと化している。
事業資金の調達と、立地に見合った不動産収益確保のための超高層化。
その免罪符としてのイメージ保存(継承)だ。
背後に建つ超高層棟は、極力目立たない外装とするか、保存部分のイメージと抗わないデザインが採用される。
今回も、例外なくそのパターンではあるが、和の意匠を基壇とした超高層は、ひょっとしたら初めての試みかもしれない。
でも、根本的なところで、新鮮味はもう無い。
どうせなら、キッチュな現況そのままに、超高層部分も思い切りコテコテの桃山風にするくらいのデザインがあっても面白かったかもね、などと思ったりもする。
歌舞伎座の界隈に、白井晟一設計の親和銀行東京支店(銀座店)があったが、既に取り壊されている。
この歌舞伎座も建て替えとなると、残る特異な建物は三原橋観光館(三原橋地下街)くらいか。
土浦亀城の設計といわれる1952年竣工のこのレイトモダンな建築は、晴海通りの両側に対面しつつ地下街で連結する構成。
周囲を高層建築で囲まれつつも不思議な存在感を放っている。
|

|
|

|
|
|
2009.01.31:過激な賃貸
|
|
※1:
ちなみに、景観を乱すとした原告側近隣住民の請求を棄却する地裁判決が最近出された。
|
|
|
1月17日にこの場で分譲と賃貸について述べた。
ニッチなマーケット相手に成り立つビジネススキームとしての賃貸事業も有り得る旨を少々書いたが、その端的な例を見かけた。
あまり熱心に読む雑誌ではない「カーサ・ブルータス」の2009年2月号に、それは載っていた。
題して「楳図かずおの紅白の部屋」。
楳図かずおの基本デザインに基づき、既築マンションに内装リフォームを施した賃貸住戸だ。
調べてみると昨年4月に既に完成していた物件らしいが、私はこの雑誌で初めてその存在を知った。
インテリアは赤と白のストライプが大胆に採用され、氏の作品のモティーフも所々にちりばめられている。
掲載されている写真のインパクトに、思わずに視線が釘付けになった。
手がけた事業主は「明来」。
記事によると、楳図かずおにオファーするきっかけが、外観デザインを巡って訴訟を起こされた氏の自邸であったという※1。
ただし、単なる興味本位では無いところが凄い。
曰く、「芸術は賛否両論があるから成り立つ」。
タダモンのディベロッパーではないな、と思い同社のサイトを見ると、これまた何だか凄い。
「10人中9人に嫌われるという考え方」とは、文字通り逆転の発想。
そして賃貸マンション事業だからこそ成立する。
目下、「テーマパークマンション」と銘打ち「楳図かずおの紅白の部屋」に勝るとも劣らぬインパクトのプロジェクトが複数進行しているようだ。
しかし、そのマーケットはある程度限定されるのだろう。
それに、強烈なインパクトゆえに消費されやすく、従って事業の継続性も未知数ではないか。
この手の(と、一括りにするのは失礼かもしれないが・・・)一風変わった物件を紹介するテレビ番組を時折見かける。
それらのプロジェクトの「その後」がどうなっているのか、少々気になるところでもある。
「カーサ・ブルータス2009年2月号」には、これ以外も、セキスイハイムの新作「クレスカーサ」が紹介されている。
「どことなく<セキスイハイムM1>に似ていませんか?」と紹介されているが、全然似ていないと思う。
ただし、ユニット工法住宅は本来こうあるべきなのではないかと思わせる外観ではある。
M1以降の同社の歴史は、ユニット工法的な雰囲気の払拭の歴史ではなかったか。
その結果として、殆どのラインアップが何とも中途半端なデザイン。
そしてそれとは逆に、生産性の面で工法のメリットが十分出し切れていないのではとの印象もあった。
デザイン性と生産性のバランスは、「住宅メーカーの住宅」のミサワホーム55のページでも少々言及したが、なかなかに難しい課題ではある。
その点、この「クレスカーサ」は、ユニット工法の特性を活かしながらも洗練されたデザインにまとめられている様に見える。
でも、やっぱりM1ではないと思う。
同誌には、これ以外に宮本佳明設計の「ハンカイハウス」も掲載されている。
作品そのものはともかくとして、対談の中で述べられている「補強というと、壁をがっちり固めれば大丈夫だと思われがちだけれども、本当は違うんですよ。」は、重要なところ。
このことは、また別の機会に書いてみたい。
|

|
|

|
|
|
2009.01.24:都立図書館
|
|
|
|
暫し閉館していた東京都立中央図書館が、1月4日にリニューアルオープン。
当館のみに所蔵されている資料も少なくないため、早速出向く。
相変わらず館内のセキュリティは厳重だけれども、IT化が進んで図書の貸し出しに関する運用が随分変わった。
戸惑う利用者も多いようで、検索端末のまわりには職員が多数張り付いていた。
どの人も親切かつ丁寧に応対しているようであったが、図書館ってこんなに沢山職員がいたのね、と少々驚いた。
更には、都議会議員とおぼしき人が視察に訪れていたりと、しばらくは慌しい状況が続くのであろう。
ともあれ、やはり蔵書の充実振りは流石。
勿論、蔵書数となると国会図書館が一番だ。
しかし、都立図書館は日曜や祝日も開館するし平日も夜遅くまで開いているから利用しやすい。
そして、麻布の高台という立地条件も良い。
5階にあるカフェテリアからは、都心が一望できる。
メニューはどれも安くて量も多い。
雰囲気はいかにも公共施設の食堂だけれども、麻布というロケーションでこの値段と眺望はかなりの穴場といって良いだろう。
貴重な蔵書と戯れつつ、疲れたらカフェテリアで気分転換。
こんな休日の過ごし方もたまには良いではないか。
そして帰り際に、有栖川宮記念公園側に隣接する「ナショナル麻布マーケット」をのぞいて見るのも良い。
世界中の珍しい食材がそろっていて、それらを観て廻るのも結構面白い。
大使館街という土地柄、様々な国の人達が買い物に来ているから、ちょっとばかり国際都市東京といった雰囲気も堪能できる。
以前、勤務先の事務所が南麻布にあったころは、時折ここでウルケルを買って帰ったな。
都立図書館は中央図書館の他に、多摩図書館と日比谷図書館がある。
このうち、日比谷図書館は千代田区に移管されるため、今年の4月1日から当面休館するとのこと。
建物の老朽化や都の財政難等から以前より存廃が検討されていたのだが、区に移管という形でとりあえず建物自体は延命される模様。
ユニークな形の建物で以前から気に入っていたので、まずは一安心。
ということで、この日比谷図書館を建築探訪のページに載せた。
|

|
|

|
|
|
2009.01.17:雑誌雑感
|
|
|
|
日経アーキテクチュア2009年1月12日号
「巻末特別企画」と銘打って、建築をテーマにした読み切り漫画を四本立てで掲載。
巻末とか言いつつ、実際には大半を漫画に割く建築専門誌としては恐らく前代未聞の試み。
個人的には、当雑誌の編集者でもある宮沢洋作・画の『「建築士」「建築家」をめぐる闘いの100年史』が勉強になる内容で印象に残った。
もっとも、内容はタイトルの様な崇高なモノではなく、むしろ『建築業界団体をめぐるドタバタの100年史』といったトコロではあるが・・・。
新建築2009年1月号
巻末に連載されている「月評」については、この雑記帳の場でも何度か述べている。
年が変わるのと同時に、その執筆担当が変わった。
昨年の執筆者の一人、原広司の月評があまりにも凄すぎたためか否かは勿論判らぬが、今年の担当者には林昌二と植田実が名を連ねている。
いずれも重鎮、業界の御意見番。
適切な月評が展開するのだろうと期待しつつ、目を通す。
林昌二の月評は、極めて平易で穏やかな文体。
冒頭で、妹島和世の「大倉山の集合住宅」について、分譲ではなく賃貸で実現したことに驚きを表明している。
この雑記帳の場で何を書こうが単なる遠吠えだが、しかしこの論評は少し違うと思う。
この手の先鋭的な集合住宅は、恒久的な所有権を伴わない賃貸という契約形態だからこそ事業が成り立つものだろう。
つまりは、任意の期間、面白い建築空間を堪能してみたいといった層がマーケット。
例えば、荒川修作+マドリン・ギンズのデザインによるあの三鷹養老天命反転住宅だって、最初は分譲だったけれども今は賃貸で運用されている。
それ以外にも、時折建築ジャーナリズムを賑わす奇抜な集合住宅の多くは賃貸だ。
コンフォルト106号2009年2月号
「特集 美しく育つ素材」が興味深い。
「時間仕上げの家」とは、琴線に触れるコトバ。
紹介されている経年と共に味わいを増す数々の素材には憧れを持つ。
とは言え現実は、時と共に劣化する以外の選択肢を持ち得ぬ新建材に囲まれる日々。
そういえば、前述の日経アーキテクチュアを発行する日経BP社のサイト「ケンプラッツ」のコラムの中で話題を呼んだものがあった。
『“なんちゃって天然木”に一言』と題したそのコラムと、そのコラムに対する感想として載せられた夥しい量の書込みは、多くの新建材に共通する課題を示唆している。
|

|
|

|
|
|
2009.01.10:建築と鉄道
|
|
|
|
最近、いつも通勤に利用している鉄道路線に新型車量が導入された。
私は鉄道には詳しくないし興味もない。
地元のbbsにそんなスレッドがあったのを見知っていた程度であった。
この前の休日、たまたまその新型車両に乗る機会があった。
しかし、なんだかいつもと雰囲気が違う。
高級そうな一眼レフカメラを首からぶら下げた乗客が多々目に付く。
いずれも鋭い目つきで車両の中を見渡している。
更には、天井面のスピーカーにボイスレコーダーをかざし、車内放送を録音している人。
車窓が熱線吸収ガラスだとか何とかブツブツ会話しつつ走行中の車内を徘徊する面々。
そして各駅のホームの端部には、カメラを構えている集団。
言うまでもない。
新型車両を一目見ようという鉄道マニアの人たちなのだろう。
普段見慣れぬ様態に、思わず三文字の形容詞が脳裏をかすめかけるが、そこでチョット待てヨとなる。
対象が変われば私も似たようなものかもしれぬ。
そう、鉄道を建築に置き換えれば、彼らと大して変わらないじゃないか。
もっとも、フィールドワークはなるべく身軽にと思っているので、大きなカメラは持ち歩かないし、そもそも持ってもいない。
ともあれ、彼らは彼らなりに一般人には気づかぬ事象に極上の価値観を見出し、そして至福の時間を堪能しているのであろう。
後で調べてみると、件の新型車両は、車体の横幅が15cmほど広くなっているのだそうだ。
画期的なことらしいが、私は混雑のピークを避けて通勤するようにしているので、その工夫の恩恵にはあまり与ることは無いのだろう。
しかし、本格的な通勤ラッシュの時間帯には効果があるのではないか。
様々な規制や条件の中で、可能な限り内部空間のアメニティを高めようとする工夫や技術開発は、建築にも通じるものがある。
そういえば、建築と鉄道のコラボレーション事例もある。
例えば、若林広幸が車両デザインを手がけた「南海空港特急ラピート」。
同じく、岡部憲明による「小田急電鉄特急ロマンスカー」。
ミサワホームも寝台特急の個室のインテリアを担当している。
調べれば、他にもいろいろ有るかもしれない。
|

|
|

|
|
|
2009.01.04:年賀状
|
|
|
|
正月。
年賀状が届く。
この一年に一度の機会でしか音信を確認しあえなくなっている人も何人かいるけれど、しかしこうやって一年の最初に無事を伝え合うのは、とっても良い習慣だと思う。
 私から送った年賀状に貼り付けた画像の元ネタは、右の画像。
昨年訪ねた古民家の奥座敷の間仕切襖だ。
その全面に花鳥が描かれている。
私から送った年賀状に貼り付けた画像の元ネタは、右の画像。
昨年訪ねた古民家の奥座敷の間仕切襖だ。
その全面に花鳥が描かれている。
最初に目に留まった際は、随分コテコテなしつらえだなといった印象。
しかし、よくよく観ると、とっても繊細な襖絵。
かつて飼っていた猫に引っ掻かれてしまったとのことで、所どころ欠損していた。
しかし日当たりの良い部屋に面しているにも関わらず、色褪せは少ない。
その美しさに思わずカメラを向ける。
長い期間にわたって紫外線を浴び続けて来たのだから気にすることは無いかもしれないと思いつつ、念のためにフラッシュを使わずに撮影した。
住人の話では、残念ながら絵の作者は判らないとのこと。
登録有形文化財への登録を申請予定の古民家なので、ひょっとしたらその過程で作者が判明するかもしれない。
新建材を纏ったチープな建物が連なる町並みの中にやや控えめに建つ古民家の奥に、このような極上の佇まいが秘めやかに残されているというのが、何とも奥深い。
そう、外観だけでは佇まいの本質は見えてこない。
内観まで追求することが大切なのだろうけれども、しかしそれはなかなかに難しい。
|