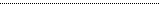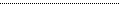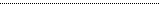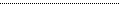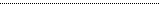|
|
2010.06.29:15周年
|
※1:
 今はもう起動しなくなってしまったPC-9801 NX/C。
今はもう起動しなくなってしまったPC-9801 NX/C。
でも、入手経緯を思えば処分することは出来ない。
|
|
|
|
@niftyに私が入会して丸15年が経過した。
入会した頃は、まだ@niftyがNIFTY-Serveと称し、そこで行われる事業が「パソコン通信」と呼ばれていた時代である。
入会のきっかけは、設計図書の作図にJW_CADというフリーウェアのCADを使用するようになったことであった。
同ソフトの市販マニュアル本の巻末に付いていたイントロパックを使い、四苦八苦しながら接続環境の個人設定を行った記憶がある。
始めたばかりの頃は、一級建築士合格祝いに親がプレゼントしてくれた、PC-9801 NX/C※1というNEC製のノートパソコンを使っていた。
従量制の接続料を抑えるために、会員が作成したフリーウェアで、「フォーラム」や「パティオ」というNIFTY-Serve独自のサービスを自動巡回していた時代をリアルタイムで経験した、恐らくは最後の方の会員ということになるのだろうか。
今から思えば既に十分隔世の感を持つ。
しかし当時は、それまでに経験したことのない広大なネットの世界が広がっているように思えた。
見知らぬ人と、共通の話題について情報を共有できること。
あるいは、そのような環境でなければ入手し得ぬであろう情報に接することが出来ること。
今では当たり前のこれらのことが、とっても画期的であった。
そして今とは異なり、確実で良質な情報を容易且つ安全に入手できた様にも思う。
思い起こして特に印象に残っているのは、北海道の豊浜トンネルで起きた大規模な崩落事故※2現場で救出作業に携わっていた人による、とあるフォーラムへの書き込みだ。
未曾有の事態に立ち向かう現場における、関係者の苦悩と懸命の作業。
そこには、遠く離れたテレビ局のスタジオにて繰り広げられる、作業の進捗に対するコメンテーターや評論家連中の批判じみた偉そうなお喋りとは全く異なる現実が存在した。
そんな状況を文字媒体を通じて知り、マスコミによる報道とは異なるネットの力を実感した。
あるいは、建築と全然関係無いフォーラムで、当時建設中であった京都駅ビルに対するかなり高度な議論が展開されていたこともあって、リゾーム状の情報の広がりを感じた。
北海道関連のフォーラムでは、関東でラム肉やジンギスカンのタレを売っている店の情報が飛び交っていた。
羊肉の評価が不当に低かった当時の関東の食事情においては、それがとっても切実な情報であったという元北海道民は私だけではなかったようだ。
また、NIFTY-Serveが縁で今でも続いている付き合いも有る。
そんな事々を思い起こすと、15年間使い続けているniftyのIDにも、何となく愛着が感じられてくる。
だから、まだしばらくは@niftyの会員であり続けるであろうと思う。
|
|
※2:
1996年2月10日に発生。
トンネル上部の、体積1万立方メートル・重さ2万7000トンに及ぶ岩盤が崩落した。
鰊番屋を観て廻るために何度も通ったトンネルであり、他人事では無かった。
|

|
|

|
|
|
2010.06.26:雪の隠喩
|
|
|
|
建築探訪のページに、雪氷防災研究センターを載せた。
国の機関なので、その時々の組織改変に伴って、名称が幾度も変更されている。
私が長岡に在住していた頃は、「雪害実験研究所」であった。
だから私の中では、この施設の名前は今でもこの「雪害実験研究所」である。
パッと見た目には凡庸な建物かも知れぬ。
しかし、仔細に見てみると、なかなか興味深い建物ではないだろうか。
小学生の頃、社会科見学でこの施設を訪ねたことがあった。
昔のアルバムには、その時撮影された写真が幾つか保管されている。
その中の一枚に、車寄せキャノピーの前に設けられた池のほとりで、水の中を泳ぎ回る鯉を眺めている写真がある。
 そんなに大きな池ではなかったが、現在も右の写真の通り同じ場所に池がある。
といっても、かつてよりも更にこじんまりとしたものに変わってはいるが・・・。
そんなに大きな池ではなかったが、現在も右の写真の通り同じ場所に池がある。
といっても、かつてよりも更にこじんまりとしたものに変わってはいるが・・・。
本文の備考欄に書いた、塔屋の「かまくら」形状説と同様に推察の域を出ないので、そちらには書かなかったが、この池の意味についても、推察をめぐらすことが出来る。
果たして、キャノピーの先端に池を設けた設計意図は何か。
私にはこれも、塔屋と同様に雪にまつわる意味が込められているように思う。
つまり、自然落雪屋根の軒先に設けられた、融雪装置としての池のイメージだ。
現在でも、急勾配屋根の軒下に池を設けた民家を見かけることがある。
そのルーツは定かではないが、例えば1932年に県内の南魚沼郡大和町大崎に、50度の急勾配屋根と、その軒下に養魚を兼ねた池を設けた民家が建てられた。
地元の小学校の校長が自ら構想し建てた民家だそうだが、考現学者の今和次郎も、その民家を訪ねている。
屋根の勾配を急にすることで積もった雪を自然落下させ、その直下の池によって自然融雪する。
そのことにより、雪下ろしの重労働から解放されるという訳だ。
雪害実験研究所の車寄せキャノピーはフラットルーフだが、しかしその先端に池を配置したのは、そんな融雪池のメタファーなのではないか。
かまくら形状の塔屋といい、キャノピー先端の池といい、この建物の設計者は、雪に関わることをさりげなく建物に表現した。
そんな気がしてならない。
設計者は今のところわからない。
それに望むべくも無いが、しかしもしも設計意図を聞く機会に恵まれたならば、本文の方にも書いた増築案の有無も含め、いろいろと確認してみたいものである。
この建物の一階に低温室があることは本文の方にも書いた。
見学の際、その室内に入った記憶がある。
ひんやりとした空気の感触の他、なんともいえぬ匂いがあったことを記憶している。
現在、仕事で恒温恒湿実験室に入ることが時折あるが、室温設定を低くしている時に、同様の匂いを感じることがある。
そんな時、幼少の頃の記憶が微かによみがえるのであるが、嗅覚も、建築空間を記憶するうえでの大切な要素ということであろう。
本文に載せたリーフレットからの転載画像以外の写真は、二年前の夏に長岡を訪ねた時に撮ったものだ。
長岡祭りの際、高校時代の同級生の家に泊めてもらった折に、その同級生の車で連れて行ってもらった。
そんなにメジャーな施設では無いだろうから判るかな?と思ったけれど、名前を告げただけで全く迷うことなく現地まで運転してくれた。
さすがである。
数十年ぶりの建物との再開となった訳だが、外構も含めて綺麗に改修されていたため、少々違和感を覚えた。
しかし、建てられてから半世紀近くを迎えようとしている建物が、改修されながら現役で使われているというのは、嬉しいことだ。
|

|
|

|
|
|
2010.06.19:岩見沢逍遥
|
|
|
|
再建成ったJR岩見沢駅とそれに伴って再整備された駅前広場のことについては、5月15日の雑記に書いた。
勿論、この駅舎を観ることが第一の目的であったが、それまで岩見沢市内を散策したこともなかった。
だからこの機会に、少し巡り歩いてみることにした。
駅舎を一通り観てから、駅前の既存市街地に出る。
まずは、あらかじめ調べておいた南空知食糧倉庫(旧北海道銀行岩見沢支店)に足を向ける。
1925年築のRC造二階建ての建築。
大オーダーの付柱を配した古典的な意匠を簡素に纏った近代建築であるが、なぜか資料に記載されていた住所を訪ねてもそれらしき建物がみつからない。
資料に掲載された外観写真に写っている隣接建物からその建設場所と思しき場所の前に立ってみるが、そこには築浅のワンルームマンションが建つのみ。
探し方が悪いのか、それとも既に除却されてしまったのか。
まぁ、こればかりを探すことに時間を割いてもいられぬと、あっさりと諦める。
以前だったら考えられないことだが、そんな自分に少々唖然としつつ、あても無く商店街をふらつく。
歩道の多くにアーケードが掛かっているのは、積雪が多いからなのだろうか。
そのアーケードの下には、シャッターを降ろした店舗が目立つ。
そしてそのシャッターには、二種類の貼り紙が目立つ。
一つは閉店のお知らせ。もう一つがテナント募集。
この辺も、地方中核都市の既存市街地には良く見受けられる光景。
そのことをいちいち挙げつらうことに意味は無いが一つだけ現況をしめすと、写真1の通り。

写真1:休日の昼下がりの商店街
シャッターが降りたり、あるいは空き店舗となった小規模店舗の連なりの向こう側に、大規模店舗。
小規模の自営店舗が連綿と連なる一角に突如出店されたのだろう。
果たして周囲の既存商店街と共存共栄が図られていたのか、それともそれらを衰退させる結果を招いたのか、その辺の事情は分からない。
しかしその大規模店舗も、塔屋に設置された看板の表示は塗つぶされている。
屋内に入れば、1階と2階のみの営業。
しかも1階は空きスペースが多く、2階はスペースの半分が閉鎖された状態。
なかなかに厳しい現実がある。
一方でそんな状況は、性急なスクラップアンドビルドから街を遠ざけているという面もある。
いや、実際にはスクラップの方は無い訳ではない。
歯抜け状に更地となった箇所も散見される。
しかし、昭和中期頃の味のある建物が散在し、その手の建築鑑賞をそれなりに愉しませてくれる(写真2,3)。

写真2:
|
|

写真3:
|
とはいえ、それでは何にもならない。
人口減少と高齢化の進行に伴う都市の経時変化に対し、単に再開発や再整備といった手法による効果は限定的であろう。
そしてそれは岩見沢駅前に限ったことではない。
全国各地に散見される同様の都市を、今後一体どうしたら良いのだろう。
あるいは、その対処にあたって建築に可能なことはあるのだろうか。
|

|
|

|
|
|
2010.06.12:垂直動線と書店
|
|
|
|
5月26日の雑記にて、階高のことについて書いた。その中で、階の移動にまつわるストレスに関して、書店を例に書いた。
この垂直動線のことを踏まえて、いくつかの書店について書いてみたい。
ジュンク堂池袋本店:
文句無しの書籍数。
建築系の品揃えだけを見ても、「こんな本まで・・・」という書籍が平気で書棚に納まっていたりする。
雑誌のバックナンバーも豊富なところが嬉しい。
現居住地からは離れているけれども、近傍に寄った際にはついつい足を運んでしまう書店だ。
この書店における建築系図書のフロアは上階の方。
だから延々とエスカレーターを昇ることになる。
しかし、そのエスカレーターはガラス張りの外壁に面して設けられていて、外の風景を観ながら昇降することが出来る。
そのことが、ストレスを少々緩和する。
八重洲ブックセンター:
 白一色のタイル張りと、隅角部をヌメリとした曲面によって構成した外観は、今でも十分洗練されたデザイン。
白一色のタイル張りと、隅角部をヌメリとした曲面によって構成した外観は、今でも十分洗練されたデザイン。
近年改修が施された屋内一階部分の設えも良い。
その一階は階高を贅沢に取ってスキップフロアの喫茶コーナーを組み込むなど、他店との差別化を図っている。
八重洲という立地特性のためか、かつては隔週日曜日が定休日だった。
だから、日曜日に同店を訪ねて哀しい思いをしたこともしばしば。
ライバル店が丸の内側に出来たせいか、今はそんなことは無い。
ここでも建築系図書は上階の方。
しかも近年、売り場が増床され、更に上階に移動した。
そしてこともあろうに、増床されたフロアにはエスカレーターが設置されていない。
階段かエレベーターを利用することになるが、商業施設におけるエレベーターの輸送能力などたかが知れている。
しかも、そもそも客の縦移動を想定したエレベーターではなく、元はあきらかに業務用のもの。
だから主には階段を利用せざるを得ない。
一階からエスカレーターで幾層も上昇した挙句、更には理工フロアまで3層を階段で昇ることになる。
まぁ、息せき辿りつくだけの充実した品揃えではある。
それに、外壁面に大きく取られた開口部から東京駅方面の眺望を楽しめるちょっとした休憩スペースも設けられているのが、せめてもの救い。
三省堂書店有楽町店:
JR有楽町駅の真向かい。
東京交通会館の一階と二階の一部にテナントとして入っている。
建築関連図書は二階。
上記二店舗に比べると、たやすく書物に辿り着くことが出来るけれども、店舗の規模が規模なので書籍数は限られる。
書店内にも上下を往来する階段が一箇所設けられているし、交通会館ビル内のエスカレーターを利用して二階にアクセスすることも可能。
しかしここは一つ、それらとは別にビル内のほぼ中央に設けられている階段を利用したいところ。
その壁面に施された天然石によるモザイク壁画がなかなか素晴らしい。
|

|
|

|
|
|
2010.06.06:聖ミカエル教会
|
|
|
|
近所の図書館で、予約しておいた「磯崎新の建築・美術をめぐる10の事件簿 」を借りる。
何度か書店でページを開いてみたけれども、どうもページレイアウトが好きになれない。
行間に文字の大きさと色を変えた注釈を挿入するという手法に違和感がある。
そんなデザインが引っ掛かって、購入を躊躇して暫く時間が経ってしまった。
でも、内容そのものは面白そうだし、ためになる事項が一杯なのだろうと気には掛かっていたので、とりあえずは図書館で借りることにした次第。
図書館近傍の喫茶店で少し目を通す。
抵抗があった注釈の挿入方法も、読むうちに気にならなくなった。
というよりも、行間に注釈を付けておいてくれなければ、とてもじゃないが読み進むことが出来ない。
それ程に、初見の固有名詞が満載だ。
建築史のことをちゃんと勉強し、理解していれば、きっととても面白くてスリリングな内容なのだろう。
過去500年分の建築と芸術に対して縦横無尽に展開される言説の数々には、ただただ驚くばかり。
同じ著者による書籍「空間の行間」を読んだ時と同じ様な感覚に襲われた。
でもって、頭の中が建築のことで一杯になったついでに、久々にギャラリー・A4に行く。
ちょうど、「札幌聖ミカエル教会とアントニン・レーモンド展」を開催中。
 札幌駅の北方約1kmに立地するこの教会を初めて観たのは、1988年7月。
それまで、この教会の存在は知らず、市内の古民家を観て廻っている折にたまたま見つけた。
右の写真は、その時撮影したもの。
第一印象は、「古いのか新しいのかよくわからない建物」といった程度。
アントニン・レーモンドの設計によるということを知ったのは、それからかなり後のことになるが、いまだに屋内に入ったことは無い。
で、今回の展覧会にて、初めてその内観を見知ることとなった。
札幌駅の北方約1kmに立地するこの教会を初めて観たのは、1988年7月。
それまで、この教会の存在は知らず、市内の古民家を観て廻っている折にたまたま見つけた。
右の写真は、その時撮影したもの。
第一印象は、「古いのか新しいのかよくわからない建物」といった程度。
アントニン・レーモンドの設計によるということを知ったのは、それからかなり後のことになるが、いまだに屋内に入ったことは無い。
で、今回の展覧会にて、初めてその内観を見知ることとなった。
半裁された丸太が織り成す精緻な小屋組みに自然光が降り注ぐ構成は、高崎市の旧井上房一郎邸や軽井沢の聖パウロカトリック教会を髣髴とさせる。
いや、それら以上に複雑で大胆な構成を見て取ることが出来る。
機会があれば、再度訪ねて屋内も実際に観てみたい。
ギャラリーには、レーモンドの他の作品も紹介されていた。
設計図面も実物が幾つか展示されていたが、その中の一つ、「足立別邸」の平面図に目が釘付けになった。
手描きによるものだが、とにかく美しい。
要素に応じた線の濃淡の繊細な使い分けは、CADでは未だに表現不可能だ。
平面プランも美しいし、図面そのものの痛みも少ない。
作図者の個性なのだろうけれども、図面上に表記されている、数字の「6」の字の書き方に少しクセがある。
作図年月日が昭和40年5月28日となっているので、45年前の図面である。
手描きだから、CAD図の様にデータから何度でも出図できる訳ではない。
世界にたった一枚の図面である。
それが、殆ど劣化することも無く、大切に保管されているというのは素晴らしいことだ。
美しい手描き図面は、それ自体がアート作品だと再認識する。
|

|
|

|
|
|
2010.05.29:メーカーとビルダー
|
|
|
|
「週刊住宅」の5月24日号に、ミサワホームが木造軸組とツーバイフォー工法の住宅を拡販する旨の記事が掲載されていた。
同社が創業以来脈々と培ってきた独自の工業化工法とは異なる、広く一般化された工法による住宅事業を始めたのが昨年度後半。
今年度は、更に販売戸数の目標を増やすという。
住宅市場規模が縮小傾向にあるにもかかわらず、プレハブ住宅のシェアは15%程度に固定されたまま推移している。
そんな状況下では、住宅の工業化に向けた高い理想だけを掲げている場合ではないということなのだろう。
それに、大して興味も無いので気にも留めていなかったが、同じ紙面に掲載されているメーカー各社の先期連結決算の記事をみると、業界の趨勢も昔と随分変ったものだと思う。
同社としては、抜本的なテコ入れが必要と判断した面もあるのだろう。
とりあえずは、従来の同社の工業化住宅とは商品体系を分けるために、「MJ WOOD」というブランド名称を冠し、三つのモデルを発表している。
その中の一つ、「Season j」はともかくとして、他の二つは、内外観ともに恐ろしい程に凡庸だ。
中堅の地域ビルダーでも普通に手掛けるレベルといった程度の印象しか持てない。
でも、恐らくは、そんなありきたりなモデルこそが現実には良く売れるのだろうし、短期的な売上成果には確実に貢献するのだろう。
しかし、売り易いからといって、その手の商品に注力すればするほど、自社のアイデンティティは弱まりかねない。
「ハウジングトリビューン誌」3月26日号の巻頭コラムに、「プレハブ化が進む木造住宅市場へと歩を進めはじめた"元祖"プレハブメーカー」という一文がある。
「MJ WOOD」の拡販は、そんな流れの中に与するものだろう。
既に、ハウスメーカーと地域ビルダーの造り出す住宅の質の差異は、極めて曖昧なものになっている。
そんな中で、それぞれがどのようにして存在価値を維持していくのか。
勿論ミサワホームでも、前述の「Season j」や、あるいは独自のノウハウを駆使した「GENIUS 彩日の家」等々、直近においても興味深いモデルを発表している。
この二つのモデルについては別の機会に改めて書いてみたい。
また、地域ビルダー側の方にも、品質的にも商品的にも魅力的で個性的な事例が増えているのかもしれない。
そんなビルダーを探してみる気力も審美眼も持ち合わせてはいないけれども、興味の及ぶ範囲で注視してみたいとも思う。
|

|
|

|
|
|
2010.05.26:階高
|
|
|
|
ネタを随分と引きずることになるが、今回も丸専デパートについて少々。
マイ・スキップ4月号に掲載していただいた文章には、当デパートの内外観写真も幾つか添えられている。
私が撮影したものも2枚あるが、それ以外にも、貴重な画像が幾つか載せられている。
そんな中で、昭和39年に撮影された店内の写真が特に気になった。
恐らく一階部分だろうと思うが、天井が結構高い。
いや、昨今の商業施設に比べれば特筆する程の高さではない。
しかし、竣工した1960年という状況を考えれば、結構豊かな天井高という気がする。
戦前のものはともかくとして、戦後から昭和50年代辺りまでの期間に建てられたデパートの階高と、最近のものを比べると、その違いは歴然としている。
試しに、お住まいの町に建つデパートを竣工年代順に比較してみるのも面白いだろう。
徐々に階高が豊かになっているのではないだろうか。
階高と天井高は必ずしもリンクしないが、その場合は、階段やエスカレーターの昇降距離で確認してみれば良い。
階高設定には幾つかのパターンがある。
一階は豊かな天井高を確保しつつ、二階以上の基準階は低く抑えているパターン。
丸専デパートは、これに該当すると思われる。
それと、一階も含めて全て窮屈に抑えているパターン。
例えば、同じ長岡市内ならば、大和デパート(本年4月閉店)がこれにあたる。
各階を連絡するエスカレータの短さは、今となっては逆に新鮮でもあった。
あるいは、全階とも天井高が抑えられているけれども、吹抜けを効果的に設けて圧迫感を抑えつつ商業施設としての華やかなしつらえを演出しているパターン。
これもローカルな例になってしまうが、例えば札幌市の五番館旧館(閉店)。
この五番館旧館に関しては、道路を挟んで別棟として増築された新館の階高設定が高いため、途中階に設けられた道路を跨ぐ連絡通路にスロープが発生していた。
勿論、天井が高くて開放的な空間の方が、無意識のうちに買い物を楽しいものにするのかもしれない。
しかし、高層建築における縦方向の移動というのは結構ストレスになるものだ。
度が過ぎた階高設定というのも如何なものかとも思う。
例えば、東京駅丸の内口北側に位置する丸の内オアゾにテナントとして入る丸善などがそれにあたる。
初めて利用した時から、そのエスカレーターの長さが非常に気になっている。
主に利用する理工系図書が置かれているフロアは三階なのだが、辿りつくまでに結構ストレスを感じる。
だから、蔵書が豊富であってもこの書店はあまり利用しない。
別に階高設定の問題は商業建築のみに限ったことではない。
全ての建築用途にとって重要な事項だ。
しかし、商業施設は自由に出入りが可能な空間。
階高設定を確認することは容易だ。
そんな視点で、いつも利用するデパート等の階高を比較検証してみるのも面白そうだ。
|

|
|

|
|
|
2010.05.22:室蘭彷徨
|
※1:
 写真1:
写真1:
前面道路のカーブにあわせて微妙に弧を描く店舗併設共同住宅。
 ※2:
※2:
 写真2:
写真2:
四種類の屋根形状が混在する民家。
後方が不自然に除却されているなど、謎が多い。
|
|
|
昨年のGWに室蘭市を訪ねたことは、この雑記の場にも書いた。
出身地とはいえ、住んでいたのは幼少の頃の僅かな期間。
転居した後、この地を訪ねたことは無い。
だから、産まれてこのかた、初めて自らの出身地を散策する機会となった。
親を連れ立ってのことだったので、気の赴くままにという訳には行かなかったが、そんな中でも、気になる風景に幾つか出会う。
で、それらをじっくり堪能しようと、今年もGWの帰省の折に単身再度出向く。
室蘭市には、JR東室蘭駅界隈とJR室蘭駅界隈の二箇所の拠点があるようだということも、前回も書いた。
「ようだ」などと表現せざるを得ないところが哀しい。
それ程に、土地勘は皆無だ。
今回はJR室蘭駅界隈を彷徨する。
狭隘な路地裏にびっしりと店が並ぶ飲み屋街。
かつての繁栄を偲ばせる、擬洋風建築。
あるいは、いい塩梅に煤けた昭和中期頃に建てられたと思われる店舗建築。
そんな佇まいが散在する駅前の商店街を一通りそぞろ歩き。
その後、周辺も散策してみようかと、あてもなく歩を進める。
まず目についたのが、写真1※1の共同住宅。
一階が店舗、二階と三階に住戸が配置されているが、南北方向の奥行きが思いっきり浅い。
住戸の間取りが気になるところ。
恐らく、風通しがやたらと良いプランなのではないか。
階段の配置からすると、二階と三階それぞれに四住戸が配置されているようだ。
南面の外壁は、前面道路のカーブに合せた微妙な曲率を多角形で近似。
車が間髪なく往来する幹線道路に面するロケーションと相まって、無機的に窓が並ぶ無表情な外観にもかかわらず、何ともいえぬスピード感がある。
更に歩を進めると、不思議な民家(写真2※2)が目にとまる。
二階部分は、急勾配の屋根とレンガ積みの煙突、そして外壁のテクスチュアにより、一応は洋風と視認しえる設え。
そんな二階建て部分の一階前面に、緩勾配の切妻屋根を載せた玄関部分が突き出す。
そして、側面の煙突の脇に、半分に切断されたトタン葺きの入母屋屋根が寄り添う。
更にその右隣に和瓦葺きの入母屋の屋根が並ぶ。
異種形態の屋根が並置される状況は、度重なる改修や増築の結果なのだろうか。
そこには雨仕舞いの合理性もデザインの調和も大した意味を持たない。
異なる要素の唐突な組み合わせの妙を愛でるべきだろう。
更に少し歩くと、今度はゴミ屋敷を発見。
ゴミ屋敷といっても、ゴミで家が埋まっているのではなく、ガラクタを積み重ねて家のようなものが造られている状況。
この手の現場に出くわしたのは初めてだ。
パッと見た目には廃棄物の山。
しかし何となくその積層ぶりに建築的な様相が読み取れてしまう。
果たして、建築とは何か?。
ガラクタに独自の価値や美を見出し、それらを集めて積み重ねることと、メーカーのカタログを眺めて建材を選択し、それらを寄せ集めて組み合わせること。
この二つの行為の差異は何か。
そして、物を創るという行為の根源において、どちらがより高尚なことか。
まぁ、深く考えることでもあるまい。
しかし、フと、石山修武が畏敬の念(?)を込めて呼びならわした「バラッカー」あるいは「バラック浄土」という造語を思い起こした。
そこから先は急勾配の坂道。
昇りきれば市街が一望できるかもと、その坂を昇る。
しかし、すぐに後悔。
傍らの道路標識には、23%勾配とある。
そんな急峻な坂道の両脇には戸建住宅が折り重なるように建つ。
時折、近辺の居住者と思われる方とすれ違うが、その多くは高齢者。
どの人も昔からここに住んでいて、この坂道は当然の環境として日常生活に組み込まれているのかもしれない。
たとえそうだとしても、大変なことだろうと思う。
その坂の途中で撮ったのが写真3。
室蘭が、坂と港湾と工業の町であることを実感する。

写真3:坂を降りきった先に室蘭港。その向こう側に工場群
|

|
|

|
|
|
2010.05.19:草加から押上
|
|
|
|
外部鉄骨階段の手摺強度試験立会いのため、財団法人建材試験センターに行く。
同施設を訪ねるのは久々。
いつも東武伊勢崎線草加駅から車でアクセスしているので、いまだに場所を把握しきれていない。
とりあえず、戸建住宅地と工場地帯が交錯する微妙な位置に立地しているという印象は、以前のまま。
そんな施設内に、試験体となる手摺のパーツを持ち込んで水平加力試験を実施。
同じ棟内では、他社の試験も並行して行われていた。
よくは判らぬが、木軸フレームに制振ダンパーを組み込んだ構造体の面内せん断試験のようだ。
どこかの住宅メーカーが独自に開発した工法なのだろうけれども、どのメーカーかは判らず。
ただ、なんだかとても面白そう。
今まで見てきた面内耐力試験というと、静荷重ばかり。
しかし今回実施されているのは加振試験。
目的とした試験の立会いよりも、そっちの方が気になる。
水平加力試験にも注意を払いつつ、しかし半ばそれ以上は、隣の試験の方に視線が向いてしまった。
でも、とりあえず、立ち会った試験は無事目標強度を満たすことを確認。
他方の試験のことが気になりつつ、同センターを後にした。
帰路、押上で電車を乗り換える。
その際、東京スカイツリーの施工の様子を眺めようと、駅の外に出てみた。
東京タワーを超えて日本一の高さになったと頻繁に報道されたのは、つい最近のこと。
だから、さぞかし高いのだろうなと期待したのだけれども、第一印象は「アレッ?」といった程度。
東京タワーのようなダイナミックな上昇感が希薄だ。
芝公園の鬱蒼とした森の中の起伏に優雅な曲線を伴って脚を降ろし、そして天空へと突き抜けるように伸びる東京タワーとは、どうも勝手が異なる。
とはいっても、上棟している訳でも無いし、高いといってもその差はまだ僅か。
今後更に上へと伸びるにつれて、その佇まいがどのように変わっていくのか、楽しみではある。
|

|
|

|
|
|
2010.05.15:岩見沢複合駅舎
|
|
|
|
北海道在住の旧知の建築家からメールを貰う。
いつの間にやらツイッターを始めていた由。
しかし私はそのシステムをいまだに良く理解出来ずにいるデジタルデバイドの敗者。
つぶやきが繰り広げる緩い繋がりとやらの一端を、よく判らぬまま眺めるに留まっている。
さて、そのメールには、「岩見沢駅はもう見たかい?」とあった。
漏電が原因で十年前に駅舎が全焼。
その後コンペを経て昨年再建。
優れた内外観デザインが評価され、グッドデザイン賞を受賞。
更には日本建築学会賞作品賞も受賞ということまでは知っていたが、現物を拝むには未だ至らず。
それ以前に、岩見沢駅自体、北海道内に住んでいた時も含め、通過するか乗り換えに利用する程度で、全く縁が無かった。
ということで、GW期間中の帰省を利用し、岩見沢駅を訪ねる。
 写真1:
写真1:
左手が複合駅舎。
その前面に整備された広大な駅前広場の奥に、イベントホール赤レンガ。
|
|
 写真2:
写真2:
内観。ガラスのカーテンウォールの内側にレンガ積みのボリューム。
|
北の大地の風土を良く捉えた駅舎という雰囲気が、とっても良い。
とはいっても、設計は地元の建築家ではない。
東京に事務所を構えるワークヴィジョンズによるものだそうだ。
多用されたレンガの質感も、化粧方立に線路のレールを利用したカーテンウォールの素材感も、あらかじめ写真で見ていた以上に美しい。
同時期に再整備されたのであろう駅前広場のランドスケープデザインとのバランスも取れているし、駅舎を背にして広場の向かって左手に建つ公共施設「イベントホール赤レンガ」とのデザイン的な関連性も生成されている。
駅舎というよりは美術館の様な、そんな感じの佇まいだ。
実際、内部は駅の用途のみならず、地元大学や市の出先機関、あるいは市民ギャラリー等が併設されていて、それらの配置や動線計画にも無理がない。
全体のカラースキームは、レンガの質感を補完することを意識したのか、PCaの屋根スラブやコンクリート打放しの壁面、更にはチャコールグレー色に統一された鋼板パネル等々、素材を絞りつつシックにまとめている。
しかしそんな中でトイレだけは白一色でさわやかに仕上げていて、メリハリが効いている。
各所のディテールにも無理が無く、安心してそれらを堪能できるところが嬉しい。
自動販売機やコインロッカーの配置と色にも配慮がなされているし、サイン計画にも視認性を確保しつつ設計者のデザインコントロールがしっかりと行き届いている。
但し、券売機廻りだけは、なかなかそうはいかなかった模様。
後で貼られたと思われる各種表示で雑多な印象だ。
ともあれ、質の高い建築が、北の大地にまた一つ出来上がった。
 写真3:
写真3:
自販機とコインロッカーのブース。
違和感無く収められている。
|
|
 写真4:
写真4:
屋内から外を観る。この写真は駅の南北を連絡する自由通路の南端からの眺め。
駅前通りから一本東側の通りを正面に見据えることが出来る。
センターホールのみならず、施設内の要所要所からの眺望に、既存市街地との関連性を考察したプランニングを読み取ることが出来る。
|
問題は駅の周辺。
駅舎及びその前の広場が再整備されて間もないのだから、仕方のない事かも知れぬ。
しかし、既存市街地の雰囲気との乖離は甚だしい。
現況では、新たに異物(しかも極めて優れた)が突如挿入されたといった状態だ。
しかし、駅舎側には断絶を排除する設計上の配慮が既に盛り込まれている。
それは例えば、屋内に設けられたセンターホールと名付けられた二層吹抜けの空間。
そこからは、ガラスのカーテンウォールを介して既存商店街が一望できる。
そしてホールの中心軸と、その延長上の駅前通りの軸が見事に一致する。
既存都市構造に呼応した設計と解釈出来そうだ。
駅前の商店街がそれにどう応えて行くか。
今後の課題ということになるのだろう。
その既存駅前商店街の現況は、多くの地方中核都市が抱えるそれとほぼ同様だ。
そのことについては、別の機会に改めて書いてみたい。
|

|
|

|
|
|
2010.05.09:マイ・スキップ5月号
|
※1:
 マイ・スキップ5月号。
マイ・スキップ5月号。
新潟県長岡市を中心に発行されている、地元の有用な情報満載のフリーペーパー。
2001年1月創刊。
|
|
|
|
先月に引き続き、今月号※1にも文章を掲載していただいた。
というよりも、初期の打合せに基づき、とりあえず二回分の原稿を書いたという次第。
打合せといっても、全てメールでのやりとりである。
直接お会いしたことが全く無くても、打合せから記事掲載までが成立してしまうところが、面白い世の中である。
で、今回はえり芳ビル。
建築探訪のページにも載せているが、指定文字数もあり、最初から新たに文章を書き起こした。
果たして、この建物の魅力をどこまで表現し得たか、少々心許無い。
しかし、そんな文章を補完すべく、話の流れに沿って画像が巧みにレイアウトされているのは前回と同じ。
編集された方はさぞかし大変だったのではないかと思うけれど、そんな編集の妙も併せて愉しんでいただければと思う。
記事にも書いたとおり、この建物の来歴は今のところ不明だ。
郷土資料を探れば何か掴めるかと思い、図書館にて幾つかの書籍に目を通してみた。
結果、少なくとも1972年時点で既に建っていた様だ。
この年に新潟日報事業者から発刊された「城下町ながおか 明治・大正・昭和」という書籍の表紙に、市内中心部の航空画像が載せられている。
その中に、この建物を確認することが出来るのだ。
また、近年、私が見た際の外壁はアイボリー色に塗装されていたが、当時は濃いグレー色であった様だ。
今のところ、判明しているのはこの程度。
この表紙の写真は、今となってはなかなか貴重だ。
二代前のJR長岡駅も、背面からのアングルではあるが、一応確認することが出来る。
既に多くの市民にとっても忘却の彼方にあるかもしれないが、ロマネクス調の縦長のアーチ窓を連ねたそのファサードは、建築的にもとても興味深い。
駅の東口側には、「飛躍の鯉」と題された早川亜美作の巨大モニュメントも確認できる。
・・・などとローカルなことを書いても、分からぬ人には全然分からないし、面白くも無いな。
ともあれ、約40年前の画像が載る表紙をマジマジと閲覧室で眺めていた私の姿は、ハタから見ると相当怪しかったに違いない。
話がそれた。
記事は、先月号に引き続き「建物の記憶」というタイトルで3ぺージに掲載。
他にも、越後生紙の特集等々、興味深い記事が組まれている。
長岡市内を中心とした公共施設や商業施設にて入手可能。
東京でも、表参道の新潟県物産館「ネスパス」に置かれています。
機会あれば、御覧になってみてください。
|

|
|

|
|
|
2010.04.29:図書館三昧_3
|
※1:
 閲覧室の天井面。
段差が生じている部分で、PCパーツのジョイント小口面が露出している。
このディテールも意匠の一部だろう。
閲覧室の天井面。
段差が生じている部分で、PCパーツのジョイント小口面が露出している。
このディテールも意匠の一部だろう。
|
|
|
|
千葉県立中央図書館は、大高建築設計事務所の設計による。
閉架書庫以外は一つのモジュールで統一し、プレハブリケーションを意識したPC(プレキャストコンクリート)工法が全面的に採用されている。
この手法は、4月15日の雑記に書いた日本大学生産工学部図書館と同じであるが、用いるパーツのディテールや組立て方は全く異なるシステムだ。
格子形状のPCが露出する天井面の意匠が面白いので写真を撮りたいと思い、貸し出しカウンターの職員に許可を求めた。
無断撮影も何だし、一言声を掛けておこうといった程度の軽い気持ちだったのだが、ちょっと勝手が違った。
「少々お持ちください、他の者が対応しますので」と言って、職員が奥の事務室に引っ込んでしまう。
そして待つこと数刻。
別の職員が出てきて、A4無地の用紙に、名前や住所、撮影目的を記載するように求められた。
何だか大げさなことになってしまったなと思いつつ、「えぇ、いくらでも書きますヨ」と、要求された事項をツラツラと書き綴る。
更に、撮影にはその職員が立会うことに。
別にそれは構わないけれども、手元にあるのはいつもの安物の小型のデジカメ。
「何だか格好が付かないな」「こういった場合は、いかにも高級そうな大型カメラを構えて撮影しないとサマにならないよな」とか思いつつ、数枚の写真を撮る。
撮るたびに、職員が撮影した画像を確認。
なかなかに厳格な対応だ。
曰く、「他の閲覧者の顔が映らないように」とのこと。
別に、人物を写す趣味はあまり無い。
むしろそれらを極力排して建物の写真を撮りたいと考えてしまうことについては、以前もこの場に書いた。
ともあれ、まるで一昔前の共産圏の様な厳しい“管理体制”の下におかれながら撮った写真の中の一枚が左※1。
統一モジュールによる天井の構成によって規定される空間構成は増築が自由であり、建設時のメタボリズムの潮流にも合致し、興味深い。
ちなみに、館内には現行と先代の図書館の模型が展示されている。
先代の図書館は、レイトモダンな装いの瀟洒な建物であったようだ。
図書館に隣接して文化会館とその別館が建ち、これらを取り巻く公園と一体になって、県の文化センターを形成している。
文化会館も、同一設計者の手による。
ということで、1960年代の大高正人ワールドを存分に堪能することが出来る貴重なエリアだ。
|

|
|

|
|
|
2010.04.25:レゴブロック
|
※1:

|
|
|
|
知人のブログにレゴブロックのことが書かれていた。
幼少のみぎりに親に買い与えられて随分と遊んだ記憶がある。
昔のアルバムの中には、歯車のパーツを組み合わせて風車の様なものを作り、神妙な顔付きで動かしている様子を撮った写真が残されている。
ひょっとしたら、親が組み立ててくれて、それで遊んでいただけかもしれぬ。
自分で意識してレゴブロックを組み立てて遊んだネタとして記憶に残っているのは、長岡市立劇場。
日建設計の設計による、1973年竣工の長岡市内の文化施設。
白一色のプレーンな外観が印象的な建物だ。
その前面に整備された幸町公園のランドスケープと一体となって、整った都市空間を形成している。
竣工して間も無い頃にこの施設を訪ねて、かなり印象に残った。
で、家に帰ってからレゴブロックで市立劇場の製作を試みた。
勿論、幼少の頃の話。
劇場建築の構成などわかろう筈も無い。
体感した空間の印象のみをもとに、なにやら怪しげな物を作っていたに違いない。
しかも、ブロックの数も種類も限られる。
それらをやりくりして自分の思い通りのものを作るには、けっこう工夫が必要だったと思う。
そんな思い出のあるレゴブロックは、実はまだ手元に有る。
捨てていないから残っているという状況で、押入れの奥にずっと死蔵したままであった。
久々に出してみた状態が、左の写真である※1。
|

|
|

|
|
|
2010.04.24:プレハブの価値
|
※1:
 NEAT INNOVATOR正式発表の前年にグッドリビングショーで公開された「NEAT555」。
NEAT INNOVATOR正式発表の前年にグッドリビングショーで公開された「NEAT555」。
ユニット工法ならではのデザインでありながら、同時に新進性に富んだ住宅デザインとしても成立した外観。
(画像の出典:ミサワホーム)
|
|
|
1977年に日経新聞社から発行された「プレハブ住宅産業−停滞脱出狙う企業戦略」という書籍の巻末に、ミサワホームの当時の社長・三澤千代治と積水ハウスの当時の社長・田鍋健の対談が載せられている。
豪華な企画だ。
その中で三澤社長は、「工業化することでプレハブは一産業たりうると思う」と延べている。
対して田鍋社長は、「プレハブ住宅というのは特殊な商品ではなく、住宅産業の中の一供給形態、一工法をあらわす言葉である」と述べている。
更に、「お客さんは工法で家を買うのではない。住んで快適で、丈夫で、見映えのいいものを選ぶ。だから「プレハブ」と区切って、プレハブだけを評価するという考え方は私はとらない。」と続けている。
プレハブ住宅に対する捉え方が180度異なっていて、読んでいて面白い。
そして、近年までの両社の方向性は、それぞれの社長の言葉どおりに概ね推移してきたのではないか。
ミサワホームは、工業化に向けた技術論や手法が先行し、商品化の段階で無理やり現実にハードランディングさせたという印象の商品も散見された。
ミサワホームコアやミサワホーム55などは、その典型例だろう。
しかし、そこがとっても面白い。
住宅の工業化に向けた技術開発への拘りは、業界の中では極めて異色だ。
それに、そういったモデルがプロトタイプとなり、後に極上の住宅が具現化された例にも事欠かない。
一方で、積水ハウスはどうだろう。
どの時代においても、水準の高い住宅を供給して来たと思う。
デザインにおいても、性能においてもだ。
そして軽量鉄骨造から始まった事業も、その後、在来軸組木造,RC造,ツーバイフォーと多彩に展開して今日に至る。
しかし、個人的にはそれでもあまり魅力を感じなかった。
同じ水準の住宅を供給するメーカーは、限られるものの何社かはある。
だから、積水ハウス一社を殊更にありがたがる必要も無い。
ともあれ、この対談から約三十年を経た現在の住宅産業界の主流は、どちらの考え方に近いか。
言うまでも無い。
田鍋社長の発言の方だろう。
実際、ミサワホームでも、同社の前身時代から脈々と受け継がれてきた木質パネル接着工法や、その後開発したユニット工法といった高い工業性を誇る工法とは異なる住宅を発売し始めた。
第一弾として、1月15日にSeason jというモデルを発表。
このモデルで使われている「耐震木造住宅」という言葉には、少し違和感を覚えていた。
そして後日、その意味するところが軸組み構造と知り、少々唖然とした。
同社の中期経営計画の中に、「事業ポートフォリオの多様化」という文言がある。
その一環として木造軸組工法を事業化するというのは、前述の田鍋発言の方向性とだぶる。
もう、「完全プレハブ」への夢は過去のものか。
あるいは、1989年発表の「NEAT INNOVATOR※1」が、その頂点だったのかもしれぬ。
住宅に求められる生産性の在り方は、このモデルを境に、いや、あるいは既にそれ以前から大きく変容していたのかも知れない。
|

|
|

|
|
|
2010.04.15:図書館三昧_2
|
※1:
 南側立面の一部。
南側立面の一部。
十字形断面の柱と梁で構成されたメインフレームに、プレキャストコンクリート製のパーツが規則正しく配列される。
|
|
|
風洞試験のため、日大の生産工学部を訪ねた時の話。
アクセスには京成線の大久保駅を利用した。
この駅は過去に幾度か乗降しているが、それは日大を訪ねるためではない。
駅近傍に立地する、昭和50年代にミサワホームが造成した住宅団地内を散策するためであった。
何せ、当時リアルタイムで興味を持っていた同社の企画型住宅がごっそり現存している。
個人的にはとっても貴重な場所なのだ。
しかし、日大は駅を出て逆方向にある。
今回初めて、そちらのエリアに足を踏み入れた。
駅からキャンパスまでは「ゆうろーど」と名付けられた1km弱の長さを誇る商店街が形成されている。
味わい深い店が軒を連ねていて、歩いていて面白い。
そんな通りをひたすら北へ進むと、やがて日大の正門が見えてくる。
その正門左手に何気なく視線を向けた時、思わず目をひんむいてしまった。
そこには、建築探訪のページで紹介している栃木県庁舎議会議事堂(以下、議事堂)にそっくりな外観の施設※1が建っていた。
コレは一体、どういうことだ!
俄然、興味が沸く。
訪問の目的である風洞試験の合間を利用して、その建物を観に行く。
建物は、日本大学生産工学部図書館。
後で調べてみたところ、設計は議事堂と同じく大高正人。
議事堂竣工の四年後の作ということになる。
パーツには共通性があるが、しかし例えば、プレキャストコンクリートのポストテンション用末端部の納りや、各パーツの出隅の処理等、個々の部位には異なるディテールが散見される。
また、空間構成も、議事堂がスーパーストラクチャーを基幹とする大胆なピロティ構造が採用されているのに対し、図書館の方にはピロティが無い。
構成としては議事堂の方が面白いが、そこはそれぞれの建物に与えられた設計条件に拠ろう。
同様の構造形式を採用しつつ、個々の空間構成の要求との整合がしっかりと図られているという印象。
似ているとはいえ、単なる自己模倣に陥らぬ設計のこだわりが見て取れる。
議事堂の方は、新庁舎の整備に伴い三年前に解体されている。
その解体直前に実物を観る機会を得ていたが、再び共通性を持つ建物と出会えるとは思わなかった。
いずれ、建築探訪のページに載せたいと思う。
|

|
|

|
|
|
2010.04.11:丸専デパート補足
|
|
|
|
マイ・スキップに掲載して頂いた文章について、建築に関する個人的な印象に言及が留まってしまったと、前回の雑記に書いた。
で、もう少し追求しても良いのではないかという想いもあり、改めて調べてみようと図書館に赴く。
幸い、国立国会図書館や東京都立図書館には長岡市に関する郷土資料の蔵書も豊富だ。
そんな蔵書の中の一つ、「長岡市史 通史編」に目を通す。
上下二巻で構成されているが、下巻に市内中心街における大規模商業施設の出店について記述がある。
丸専デパートについても多くを割いているのがありがたい。
相次ぐ大規模デパートの進出に対して地元の中小商店組合が協同で作ったデパート。
それが丸専なのだそうだ。
当初は、駅前通りに面して半分の間口、しかも三階建てでのスタートであったようだ。
その当時の外観写真が掲載されている。
その後段階的に上へ上へと増築。
更に、西側に隣接していた商工会議所の移転に伴い、そちら側にも増築を行ったのだそうだ。
かつてのファサードが、左右半分ずつで異種デザインが混合された状態だったのは、そんな増築のプロセスがあったからなのだろう。
いつの頃か、その外側全面を外装パネルで覆う改修を施したのは、そんな木に竹を接いだような違和感を払拭することも目的に含まれていたのかもしれない。
ちなみに、北陸一体で初めてエスカレーターと自動扉を設置したのも、この丸専デパートなのだと書かれている。
そんな歴史に触れると、このデパートへの興味も益々沸いてくる。
・・・と、書いていて気がついたが、やはり建築的なことしか見ていないな。
まぁ、個人的な興味の対象が建築なのだから仕方が無いということにさせて頂こう。
他にも、丸専の斜め向かいに建つ大和デパート長岡店が、当初はマンション併設の10階建てになる予定だったとか、丸専に隣接するイチムラデパートの最初期の建物が木造二階建てであった等々、知らなかった事実が沢山記載されていて興味深い。
郷土資料って面白いものである。
郷土資料といえば、マイ・スキップもその面での価値が高い情報誌だと思う。
丸専デパートの記事を載せていただいた4月号では、石川雲蝶の特集も組まれている。
幕末から明治にかけて越後で活躍した木彫師。
この類稀なるアーティストの手による過剰ともいえる装飾を施した寺社建築が、新潟県内に散在する。
私は、魚沼市にある西福寺開山堂を拝観するに留まっているが、誌上で紹介されている他の作品も、是非鑑賞する機会を作りたいと思う。
|

|
|

|
|
|
2010.04.09:マイ・スキップ
|
|
|
|
新潟県長岡市を中心に発行されているフリーペーパー「マイ・スキップ」に執筆する機会を得た。
きっかけは、編集に携わっている方が、当サイトを御覧になったこと。
で、市内の建物について寄稿してみませんかというお誘いを受けた次第。
このフリーペーパーの存在は知らなかったが、送って頂いたバックナンバーにて内容を確認。
生成り色の紙が目に心地よい、タブロイドサイズ8ページの体裁。
2001年1月の創刊以来、長岡を中心とした地元の有用な情報を記事としてまとめている。
これならば安心して文章を出せると思い、原稿を書くことにした。
ということで、丸専デパートについて書く。
現存せぬ市内の大規模商業施設だが、除却されてからまだそれほど時間が経っていない。
だから、記憶にとどめている人も多いだろうし、それ以前に、多くの市民にとって馴染み深い建物であったのではないか。
そんなことから、この建物を選択した。
掲載して頂いた文章を読み返してみると、我ながら建築に関する個人的な印象の言及に留まっているという感を持つ。
本当は、どのフロアでどんな物が売られていたとか、レストラン街にはこんな店が入っていて、そこのメニューはこんなだったといったことなども書ければ、気の利いた記事になったのだろう。
しかし、そういった類の記憶は情けないことに殆ど無い。
さもありなん。
長岡に住んでいたのは高校卒業まで。
その後、かなりのブランクがある。
近年、改めて内部を観てみようと思い立って長岡を訪ねた時には、既に売り場が大幅に縮小され一階部分のみでの営業となっていた(地下も使われていたかな・・・?)。
そんな訳で、随分と偏った内容の文章になってしまったと言い訳をしておくことにしよう。
そして、そんな文章を体裁よくレイアウトしてくださった編集者の方々の技量には大感謝である。
とりわけ、文章の流れに沿った自然な写真の配置は絶妙だ。
ということで、4月発行の第111号に「建物の記憶」というタイトルで掲載されています。
市役所や図書館等々の市内主要公共施設や商業施設に置かれているし、東京でも表参道にある新潟県物産館「ネスパス」にて入手可能。
無料配布なので、機会があれば御高覧下さい。
|

|
|

|
|
|
2010.04.03:閉鎖回流
|
|
|
|
日本大学の風洞試験施設にお邪魔する。
数年前から、建物の外装にルーバーを採用する計画がやたらと増えている。
とある国内のリーディングアーキテクトが、その手の作風で破竹の勢いで実績を伸ばして来た影響が大きいのだろう。
もう、猫も杓子もルーバーである。
外観デザインに行き詰ったら竪繁のルーバーをつければ良いと思っている感が無きにしも非ず。
どうせなら、環境に配慮した日射制御の機能を担う断面形状のルーバーにするといったテクニカルアプローチでもあれば面白いのだろうが、現状ではそんな雰囲気ではない。
大した意図を伴わぬデザインが根拠となっている辺りが少々設計技術としては貧相なところ。
ともあれ、ルーバーである。
そして採用にあたっては私のところに相談が来る。
「これって、音が鳴らないでしょうかね。」
そう、外装ルーバーはいわば弦楽器みたいなものだ。
風の流れに同調して共振し、思わぬ異音を発生する場合がある。
その発生の多寡や対策ディテールの有効性検証のためには風洞を用いた試験が必要で、その施設にお邪魔するケースがこのところ随分増えている。
ルーバーの試験に関しては悩みが有った。
試験体が巨大なために大きな風洞を必要とし、適切な試験を実施できる施設がなかなか無いのだ。
固有振動に関わる問題なのでミニチュアで試験をする訳にもいかない。
財団法人鉄道総合技術研究所には、車両そのものを設置することが出来そうな巨大な風洞がある。
しかし、そんな大掛かりな施設を借りていたのでは、経費が掛かりすぎる。
そんな折、日大の閉鎖回流式風洞設備は、結構大きな試作体も扱えることが分かったので、施設を借りることにしたという次第。
日大というと、かつてミサワホームの創業者である三澤千代治が、自らが構想した木質モノコックパネル接着工法による住宅の物性試験のために通っていた場所である。
同社の前身である三沢木材プレハブ住宅部の設立以降、同大学の佐藤稔夫教授の指導を仰ぎながらの各種実験を経て、住宅の構法としては初となる大臣認定を取得したのが、1962年8月。
同年10月の日大の工学祭にて、面積20平米のモデルハウスを出展している。
そしてこの木質パネル接着工法は、今日においても同社の基本構法として脈々と使われ続けている。
半世紀前の話だから同じ実験施設がキャンパス内の残っている可能性は低いだろう。
それに試験の目的も異なる。
しかしそんな歴史のあるキャンパス内で試験に立ち会えるというのは、個人的には感慨深い。
風に起因する外装材の共振は、まだ研究途上の分野だ。
どのような風の吹き方で、どのような断面形状のルーバーが、どのような音を発生させるのか。
その確認には、大掛かりな風洞試験に頼らざるを得ない。
試験を伴わなくても済むような断面形状のシミュレーションが出来れば良いのだが、それはまだ先の話ということになりそうだ。
実際、今回の試験においても、特定の風速において試験体直近の風上に人が立った時のみ高周波の音が発生する現象が確認された。
恐らくは、人が立つことで発生する風の乱れに起因する現象なのだろう。
しかしそのメカニズムの特定には至らず。
実験室ではなく実際に設置した現場で発生したら、怪奇現象として受け取られかねない状況ではあった。
|