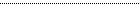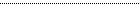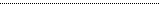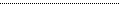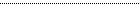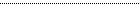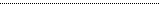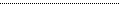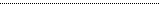|
|
2020.06.23:「気ままな街並み 日本の不思議」に対する気ままな感想
|
|
※1:
時折それが景観問題として議論されることがあっても、そこで問わるのは多くの場合「高さ」のみだ。
意匠が議論されることは極めて稀であろう。
そのことは、東京丸の内の東京海上火災ビルから始まって、近年の新国立競技場においても全く変化も進化も無い。
|
|
|
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大抑制に係るこれまでの日本政府の対応や日本人の行動に対し、他国と比して特異なものとして捉える評価をよく目にする。
それは、自粛要請という強制力を伴わぬ政府の方針決定に対し、多くの国民がそれなりに対処して取り敢えずの目的を今のところ達成しているということに対するもの。
単純な言葉で表すならば、同調性に纏わる国民性ということになろう。
ところで、読売新聞では「東西まちまち」というコラムを隔週日曜日に連載している。
6月21日は、井上章一が「気ままな街並み 日本の不思議」というタイトルで執筆しているが、そこでこのCOVID-19の感染対策に纏わる特異性について触れている。
その特異性自体は否定しない立ち位置を示しつつ、しかしそれをもって国民性の全てを語ることは出来ないとしている。
理由として挙げているのが、国内各都市の風景や景観の乱雑ぶり。
確かにこの点については、同調性の欠片も見い出せぬ状況が全国津々浦々に溢れかえっている。
緩い措置でも統制された行動をとる日本人が、なぜ街並みや景観に対する統一感の醸成には全く無頓着なのか。
この指摘は面白いと思う。
しかし、自分なりにその理由を考えてみると何となく理解出来そうな気もする。
ここで述べている同調性は、他人に迷惑を掛けないという倫理観の発動を契機とする。
COVID-19について言えば、自らが媒介者となって感染拡大の原因となり周囲や社会に迷惑を掛けてはいけないという意識が、倫理観の発動に繋がる。
一方、景観についてはどうか。
周囲に構うことなく好き勝手に建物を造っても、それが法令順守の範囲内であれば誰にも迷惑は掛からないし文句を言われる筋合いもない。
そんな認識が、建物用途や立地に拠らず国内においては一般的な価値観なのではないか※1。
そこに同調性に至る倫理観が介在する余地は無い。
国民性としての同調行動はあらゆる対象について無条件に展開され得るものでは無く、倫理観に基づく価値判断によって仕分けられる。
つまり、コラムの指摘は別に不思議なことでも何でもないという捉え方が可能なのではないか。
では、日本において「気ままな街並み」が倫理観と無縁に成立する理由は何か。
それは結局のところ、不動産とは土地のことであり、そこに建つ上屋は単なる耐久消費財という扱いだからなのではないか。
古代から続く式年遷宮も含め、上屋は仮のもの。
古くなったら建て替えるのが当然。
永続性など求めない。
その様なものに倫理性を求める意味もない。
だから、その時々の経済情勢や都市の趨勢に応じ、必要な建物を建てて消費し、無用になったら老朽化や耐震性の不足を理由に取り壊して新たな建物を建てれば良いという思想。
そこに周囲との調和や配慮が醸成されるきっかけが入り込む余地などあろうは筈もないということなのではないか。
有史以来のその様な意識を変えるためには、建築を不動産ビジネス上のフローとして扱うのではなくストックと捉える価値観の深化が必要なのだろう。
|

|
|

|
|
|
2020.06.17:多種メディア展開
|
|
|
|
一つの作品をそれ以外のメディアで再構築するノベライズとかコミカライズと呼ばれる行為には、いわゆる「コレじゃない感」を如何に回避するかという点が大きな課題として常に圧し掛かる。
好評を博したがゆえに他メディア展開が図られる経緯から鑑みれば、まずは最初の表現媒体の印象が強く付き纏うことになる訳で、そのハードルを突破することはなかなかに容易ではない。
それを乗り越えた好例としては、例えばNHKで放映されたアニメ作品「映像研には手を出すな!」などがあろうか。
アニメの制作を主題とする漫画が原作であるが、アニメ化されることでアニメ制作そのもののプロセスが巧く入れ子構造となって原作の魅力がより一層際立つ作品に仕上がった。
ここで「入れ子」と表現したことについて、例えば青木淳も、御自身の近作「京都市美術館」に関し新建築5月号に寄せた論稿「継ぎ目がないのに切れている」の中で以下の様に述べている。
|
設定画を見ていたつもりが、いつの間にか設定画の中で動き始める.
これをアクチュアルな世界とヴァーチャルな世界の混交と言うこともできる.
でも,それが起きているのがそもそも,アニメというもうひとつのヴァーチャルな世界の中でのことなのだから,むしろ大切なのは,そのレイヤー間の継ぎ目のない移行の方である.
|
歴史的建造物の改修工事に伴う既存部と新築部というレイヤの接続の在り方に関し、当該プロジェクトで実践した手法を解説するために「映像研」を大真面目に引き合いに出しているところが面白い。
ともあれ、そんな異相の入れ子に関し、アニメーションという手段が「映像研」では極めて理想的に作用し、原作の魅力をさらに際立たせた。
そこには「コレじゃない感」が介入する余地は一ミリたりとも無かった。
因みにその後実写化もされているが、そちらの方については言及を避けることにしましょうか。
個人的には、初回の途中で視聴を断念することと相成った。
他メディア展開に関し最近目にした作品として、「異世界居酒屋のぶ」についてはこの場にも幾度か書いている。
小説を原作とし、その後コミカライズ、アニメ化、実写化と様々なメディア展開が図られている。
私はアニメから入り、その後コミカライズ、そして原作へと接する順序を踏んだが、気に入っている表現媒体はコミカライズだ。
アニメよりもより繊細に、そして深く原作の世界を表現しているという印象。
然るに、最近WOWOWプライムで放映されている実写版については料金を払ってまで視聴すべきか否か逡巡した。
「映像研」の実写化の例がありますからね。
でも一方で、これも以前この場で言及した「チャンネルはそのまま」の様な実写化の佳作もある。
取り敢えず動画サイトで初回分が無料公開されていたので試しに視聴してみたが、ちょっと残念でしたかね。
異世界の住人達が、ジャガイモのことを原作に倣って「カルトッフェル」と呼ぶならば、乾杯の音頭についても同様に「プロージット」を踏襲してほしかった。
といった程度のことから始まって、「コレじゃない感」が多々散見されましたか。
|

|
|

|
|
|
2020.06.10:デパート建築
|
|
|
|
三越といえば、長い歴史と格式を誇る日本を代表する百貨店。
その本拠地である日本橋本店ともなれば、それは豪華で美しくて格調高い建築であって当然。
普通ならばそんなイメージや期待を持つところだ。
実際、館内に設えられた豪壮且つ絢爛な五層吹抜けの中央ホールなどは実に見事。
そのホールを中心に、そこかしこに老舗ならではの格調を感じるディテールが散見される。
しかし、店舗が面する室町通りの向かい側から眺める建物全景は、意外にあまり感心出来るものとは思えぬ。
相次ぐ増改築によって何やら雑然とした雰囲気を呈し、これが国内でも指折りの百貨店の本店としてふさわしい在り姿かというと少々寂しい気分になってしまうところが無きにしも非ず。
その増改築に纏わるプロセスの詳細や建築的考察については、論文も発表されている。
私が目にした関西大学助教・野村正晴の論文「三越日本橋本店の建築計画の変化と収益性」によると、そのプロセスは五期に及ぶそうだ。
論文にはそれぞれの段階の平面図も示されており、例えば象徴的な中央ホールにも様々な変遷があったことが判って興味深い。
施された増改築は、震災復興以外は、経済成長とそれに伴う人々の消費意欲の肥大、あるいは商空間の在り方に関する時代の変容等に逐一対応したものだ。
更に経営者側のシビアな事業判断も絡まり、結果としての現在の建物の様態は、1914年竣工時の意匠を中途半端に踏襲しながら上へ奥へ横へと継ぎ足され続けて来たモノ。
そこに歴史的建造物が纏う筈のしみじみとした深い味わいは見い出しにくい。
それでいて、経年によるくたびれ感も隠しおおせぬ。
改善すべく、屋内一階部分の改修を隈研吾に依頼。
氏特有の「パラパラ」な装いで今風に一新した。
その出来栄えは、流石だなぁ・・・と素直に感心させられる。
しかし今風であればあるほど、外観の現況とのギャップによって「イタイ若作り」的な印象が付与されてしまった感も否めぬ。
しかしあるいはそういった事々の全てが、途方も無い消費欲を充足し、あるいは刺激する物理存在としての百貨店という存在そのものに他ならぬということなのかもしれぬ。
そしてそれは何も、三越の日本橋本店のみに限ったことでは無い。
全国津々浦々の古くからの商業エリアにおいて、市勢の拡大や人々の暮らしの向上・多様化に合わせてデパートが次々と誕生。
事業の拡張とともに増改築が繰り広げられた。
それは、都市の興隆の在りようと一心同体。
その増改築の過程を追うことは、都市の歴史を別の視点で読み解く機会ともなろう。
だから例えば、かつて私が住んでいた新潟県長岡市が編纂した市史においては、戦後復興期の記録の項に駅前商店街のデパート建築の増改築の変遷が一部ではあるものの言及されている。
果たして、そういった視点でのデパート建築の研究というのは、体系化されているのだろうか。
近年、あらゆる地域に見受けられる既成市街地の商業地としてのポテンシャル低下に伴い、その盛衰の表象媒体としてのデパートの閉店および除却が相次いでいる。
個々の増改築に纏わる経緯や実施状況、そしてそれによって生成された様態等の記憶が失われてしまう前に記録に留める価値が十分にある様にも思えるのだが。
|

|
|

|
|
|
2020.06.05:メーカー住宅私考_118
|
※1:
発売当初は、単に「セキスイハイム」であった。
その後、新たなモデルを発表するにあたり、その名称をセキスイハイムM2と定めた際に、初期モデルにもM1の呼称が追加された。
ちなみに、「M」はモデルの意味。

※2:
新建築1984年4月臨時増刊「住宅の工業化は今」の巻頭に、内田祥哉とミサワホーム創業者三沢千代治の対談が掲載されている。
その中で、積水化学工業が1970年開催の第一回東京国際グッドリビングショーに出展したセキスイハイムのプロトタイプモデルについて、「すごいなァと思いましたね.あれはセンセーショナルでした.」と三沢氏が述べている。

※3:
「パ」はパネル、「コ」はコア、「カ」はカプセルを指す。
構造体のパネル化。設備のコア化。そしてそれらを統括したカプセル工法へと、住宅生産施工技術を高度化させる構想。
|
|
|
第117回の続きで、ミサワホーム555に関する話を綴る。
最下階の「余暇室」から最上階の「屋上健康室」まで、半層づつスキップして全体で6層のフロアを持つ動的な空間構成。
しかも、屋上健康室は屋根面が全てガラス張り。
そして余暇室はサンクンガーデンを介した半地下室。
主寝室に接続する書斎は天井高が通常の1.5倍。
和室は、外観からは想像し得ぬ意外に本格的なもの。
これらを含め、何やら楽し気な日常生活が容易にイメージ出来そうな諸室が階段の昇降と共に目くるめくように展開する。
 その華々しい住空間は、元々このモデルが正式発売に先立って1981年に開催された第14回国際見本市に出展(右図)されたことと無関係ではあるまい。
ハレの舞台に相応しいモデルを展示することで自社の商品的魅力を高くアピールする。
ために、現実性からやや遊離したデモンストレーション的な要素も加わる。
その華々しい住空間は、元々このモデルが正式発売に先立って1981年に開催された第14回国際見本市に出展(右図)されたことと無関係ではあるまい。
ハレの舞台に相応しいモデルを展示することで自社の商品的魅力を高くアピールする。
ために、現実性からやや遊離したデモンストレーション的な要素も加わる。
そんなモデルをそのまま商品化してしまうというのは、往時ならではの勢いであろうか。
「これから暮らしはもっと楽しくなる。」という明るい近未来予測に沿った先導的な住まいの具現化。
しかし、現実の住宅市場においてどの程度受け入れられたのだろうか。
発売以降、少なくとも私は最近に至るまでその施工事例を目にすることは皆無であった。
昨年と先月、広島と宮城でそれぞれ一件ずつ事例を見つけたことは結構大発見なのではないか・・・などと独り勝手に悦に入っているくらいだ。
そんな同モデルが発売された背景について、先行モデルであるミサワホーム55と対になった鮮やかな二刀流の発露と前回述べた。
しかしそれとは異なる見方も可能だ。
例えば、ユニット工法による住宅施工方法で既に先行していた積水化学工業のセキスイハイムへの対抗意識。
積水化学工業は、同工法ならではの意匠を敢えて強く押し出したセキスイハイムM1※1で鮮烈なデビューを果たすと共に、業界内の大方の評価・予測を裏切り瞬く間に事業採算ラインを上回る販売実績を達成。
以降、後継モデルを次々と投入。
順調に業績を伸ばしていた。
その成功を目の当たりにして陸続と現れた後発メーカーは、しかしオイルショックによる景気減退で無情にも多くが淘汰。
かような経緯で同工法のトップランナーに君臨した感のある同社に対し、ミサワホームが全く意を介していなかった筈はあるまい※2。
ミサワホームでは、1971年に住宅生産の進化過程である「パコカライン論※3」を発表。
その構想に則り、木質パネル接着工法の洗練から設備のコア化の推進、そしてカプセル(=ユニット)工法へと開発を着々と進めていた。
しかし積水化学工業は、その「パ」と「コ」を経ずにいきなり「カ」を実現。
事業的にも華麗な成果を収めてしまった。
そんな状況を一気に覆す切り札として、「555」が位置付けられたといった面が少なからずあったのではないか。
ために、セキスイハイムが未だ実現していなかった冒頭に示した様々な商品提案をぎっしりとモデルの中に取り込んだ。
 しかし案外、先行する積水化学工業側は、「ミサワさんも随分無理をしているネ」と、余裕の構えであったのかもしれぬ。
そしてその余裕のままに、ユニット工法的なるものからの脱却という従来とは異なる商品企画の方向性に基づき、内外観に重厚さを付与した「ハイムグロワール(右図)」を同時期に世に出している。
しかし案外、先行する積水化学工業側は、「ミサワさんも随分無理をしているネ」と、余裕の構えであったのかもしれぬ。
そしてその余裕のままに、ユニット工法的なるものからの脱却という従来とは異なる商品企画の方向性に基づき、内外観に重厚さを付与した「ハイムグロワール(右図)」を同時期に世に出している。
ミサワホームにも、そして積水化学工業にも業務上全く関わりの無い私にとって、ここまで書いたことは当然のことながら勝手な推測・妄想でしかない。
しかしそもそもタイトルを「私考」としていますからね。
でも、そんな風に好き勝手に想いを巡らせられることが、往時の住宅産業界の面白さでもある。
|

|
|

|
|
|
2020.05.29:メーカー住宅私考_117
|
|
|
|
|
このシリーズの第101回(2019年2月4日)で、ミサワホームが1982年4月28日に発売したセラミック系のモデル「ミサワホーム555」の実物を拝んだことについて書いた。
当時の同社の総合カタログや広報誌等で初めて見知って以降、実際に建てられた事例をそれまで一度も見る機会に恵まれなかった、言わば謎のモデル。
第101回の時も、「あるいはもしかするとモデルハウス以外に実際に人が住む家として建てられたケースが無かったのではないかとさえ疑っていた。」などと書いたが、願わくば実物をこの目で観てみたい。
長年、その様に思い続けてきたモデルであった。
従って昨年、当該モデルが掲載された中古住宅販売サイトに偶然目が留まった際には、モニターの前で独り心を躍らせたものだった。
矢も盾もたまらず所在地である広島市に向かい大いに眼福に授かった顛末については、第101回に記している※1。
そんなミサワホーム555に関し、再び中古住宅サイトにて建築事例を見つけた。
今度は宮城。
昨年の広島で存分に視覚の享楽に浸ったので、さすがにこちらも訪ねようという気は(今のところ)起きぬ。
しかし、個人的な知見の範囲では、その施工事例が極めて少ないモデルであるがゆえに、とても貴重な“発見”だ。
サイトに載せられた内外観画像を見ると、広島の事例と同様にこちらも竣工時の様態を一部を除き極めて良好に保持している様だ。
それらの画像に見入りつつ、同モデルの位置づけについて改めて想いを巡らしてみた。
当該モデルが発売される前年、1981年1月に、同社ではこれとは別に「ミサワホーム55」を発売している※2。
「新住宅供給システムプロジェクト」という旧通産・建設両省主催の先導事業の採択モデルとして商品化されたもの。
ローコストで高品質な住宅の大量供給を目的とした同事業の趣旨に沿い、コンパクトに纏められつつ、先進の住宅生産技術がぎっしりと凝縮されたモデルであった。
一方、「ミサワホーム555」は、同じ生産方法を採りながら、様々な商品提案を反映させた大掛かりなもの。
両モデルの概要は、「住宅メーカーの住宅」のページの内容と被るのでここでは繰り返さぬ。
この「55」と「555」の方向性の違いに、当該シリーズの第115回で指摘した同社の鮮やかな二刀流ぶりと同様の立ち居振る舞いを見い出すことが出来まいか。
つまり、高度な工業化から自在な商品性付与まで、両極端を同一構法で華麗に実現して御覧に入れますという姿勢。
これは、背景としてミサワホーム55の外装部材に採用されたセラミック系の新素材及びユニット工法の開発が、先導事業採択以前から同社が開発を進めて来たものであることと深く関わろう。
創業以来手掛けてきた木質パネル接着方式による独自の施工方法とは異なる新素材・新工法を投入することで事業ポートフォリオの拡張を図ろうという試み。
その研究開発が先導事業への採択によって国の支援を受けることとなり、意向に沿ったローコストな「国民住宅」としての「55」が商品化された。
この流れからすれば、同工法及び素材は、ローコストモデルのためのみに使用される道理は無い。
そちらの商品展開も進める一方、多様な展開の可能性も追求する。
その成果の一つが「555」だった、という位置づけが可能なのかもしれぬ。
|

|
|

|
|
|
2020.05.21:メーカー住宅私考_116
|
※1:
 ミサワホームOIII型に設定されたサンロフト。
中央上部に見えるのがその部分。
内部奥の壁の上部にハイサイドライトが見える。
このロフトに到るための箱階段が造り付けられている。
ミサワホームOIII型に設定されたサンロフト。
中央上部に見えるのがその部分。
内部奥の壁の上部にハイサイドライトが見える。
このロフトに到るための箱階段が造り付けられている。
|
|
|
前回、「家に居るということ」というタイトルで書いた内容に関連して、住宅メーカーの商品提案の動向について少し調べてみた。
すると、在宅勤務への対応を考えた事例が幾つか見受けられた。
いずれも、2から3帖程度の広さの独立した室を、その用途として家の中にレイアウトするものだ。
例えばミサワホームでは、既に2013年に「ミニラボ」と称するその様な極小空間を組み込んだ「在宅勤務応援住宅」を発表している。
他メーカーにおいても、同様の空間提案が散見される。
その極小空間と他室との接続の仕方は概ね二通りに分類出来そうだ。
一つは、セミクローズ型。
引き戸一枚でリビングや寝室等と繋がり、その建具の開閉で部屋をオープンにもクローズにも出来る。
例えば子供をある程度見守りながらの在宅勤務という場面を想定したものであろう。
もう一つが、完全なクローズ型。
他室との間に何らかのバッファーゾーンを設け、空間的にも動線的にも独立性を高めたもの。
気分の切り替えと精神の集中といった面で有意に作用することが期待されようか。
例えば積水化学工業は、寝室に二つのウォークスルークロゼットを並置し、それぞれの奥に独立した小さな書斎を設けた「パパママ個室」というプランを提案している。
共働きで且つ双方とも在宅勤務であることを想定したものだろう。
もしも私がこの様な空間を造るとしたら、バッファーゾーンの確保の方を採る。
しかし、バッファーゾーンとは何も、何らかの空間を介するということだけではない。
そこに到るまでの動線や床レベルに一ひねり加えることもバッファーゾーンとなり得る。
だから例えば、蹴上げの高い箱階段で往来する狭小なロフトというのも良いのではないかと思う。
この場合、箱階段がバッファーとして機能する。
梯子では心許ないが、普通の階段でもつまらない。
高い蹴上げをヨッコラセと昇ることで、気持ちの切り替えが促される。
日常から切り離された高みに到るという感覚が得られる。
この手のロフトの事例は数多あるが、個人的に即座に思い浮かぶのは、ミサワホームが1982年9月21日に発売したOIII型だ。
南面するハイサイドライトを組み込んだ「サンロフト」と称する小屋裏部屋を二階北側居室に連繋させるプランを仕様の一つとして設定したモデル。
そのロフトに到るために造り付けの箱階段型収納が提案されている※1。
階段を昇り、キャットウォークの様な踊り場から高さ1400mm程度の背の低い無目枠を潜って中に入ると、そこは広さ二帖半、天井高2970mmのスペース。
狭いながらも強い垂直性を持つその空間には南面するハイサイドライトから自然光が燦々と降り注ぎ、あたかも光の筒の底に佇むが如き雰囲気。
文字通り、「サンロフト」だ。
更に階下の居室と吹抜けで繋がることによって宙に浮いている様な感覚も加わり、閉じた狭隘な室で生じかねぬ閉塞性とは無縁の楽しい場所となっている。
但し、南向きのハイサイドライトは室内照度への影響が大きく落ち着いて仕事をするには不向きかも知れぬ。
原設計とは逆の北向きとした方が良さそうだ。
あるいは南面を避けるのであれば、後継モデルであるCHYLDER O2のロフトとOIII型のロフトアクセス経路を組み合わせるのも良いかもしれないな、などと空想が広がる。
ともあれ、要は独り篭って誰にも干渉されぬ「秘密基地」の獲得。
果たして今後、この様なニーズが高まるのか否かは判らぬ。
しかしそれは何も在宅勤務への対応のみを目的とするものではない。
前回触れた蟄居を愉しむための選択肢の一つとして、そんなプランのバリエーションや可能性が多様化するというのも面白いと思う。
時代が漸く、OIII型のサンロフトに追いつくのか!?
|

|
|

|
|
|
2020.05.14:家に居るということ
|
|
|
|
最近、既設ページの手直しを行い再登録する頻度が高まっている。
頻度上昇は、不要不急の外出自粛要請に対応して家の中に居る時間が増えたことと無関係ではない。
時間の増加に伴い、かつて自身で作ったページを省みる機会が増えた。
すると、いろいろと手を加えたくなって来るし、手を加える時間も十分にあるという流れ。
そもそも、当サイトの開設から十年以上を経てメンテナンスが必要なページが多々生じているという認識を以前から持っていた。
だからちょうど良い機会。
昨今の情勢については、例えばそんな風に捉えることにしている。
その自粛要請に関し、「家の中に篭っていることが苦痛」とか「外で思いっきり遊びたい」といったコメントを良く耳にする。
これはつまり、個々人の家の中での生活が味気なく退屈なものであるといった面が無きにしも非ずということの裏返しか。
勿論、外に出て愉しむことの代替を全て家の中に持ち込むことなど不可能。
しかし、もしかしたら蟄居を愉しむための改善や工夫の余地が少なからずあるのではないか。
この際、そんな視点で自らの住環境を省みてみるというのも一興。
そしてそれをきっかけにリフォーム市場が活性化し、あるいは新たな住空間の様式が生成され得れる機会となるならば、それはそれで面白いことではないか。
住まいが、それ自体が持ち得る機能を外部化し続けて久しい。
かつては仕事の場でも在った筈の住まいからその機能が喪失し、別の場所に通って業務を執り行うことが主流となった。
来客への対応や慶事や法事等々の開催も外部化。
あるいは調理や食事といった行為も外食産業の事業スキームの中に一部取り込まれている。
療養もそう。
そして近年においては有事に対する安全安心の確保という点においても、脆弱性が露呈してしまった。
更に、安寧すらも実は期待し得ないとなると、一体家とはナンだろうということになってしまう。
ということで、私自身の住環境についても考えてみる機会に充ててみようか、などと思ったりもする。
|

|
|

|
|
|
2020.05.07:万年塀に関する補足
|
|
|
|
「建築外構造物」に登録している「万年塀」のページを改訂した。
以前の体裁は、前半がその歴史、後半が当該部材に対する私情めいたものであった。
その私情の部分については、既に似た内容を「住まいの履歴」の「三番目の家」のページにて短く触れているので削除。
替わりに、この部材の意匠的なパターンについて言及することにした。
散策している折に目に留まった事例の中から二例載せることで、工業製品としての当該部材における意匠性について言及してみた。
そこに載せなかった事例をこちらにも二つ載せる。
左は、「建築外構造物」にも載せたパネルへの開孔による意匠性配慮の別事例。
下段に横スリット、最上段に四菱をあしらったパネルを組み合わせている。
横スリットは、純粋に通気の機能として塀の下部に用いた事例を良く見かける。
最上段の四菱も、プライバシーを守りつつ、外部に対する意匠的な配慮の両立を意識したものであろう。
これだけの形態操作で、プレキャストコンクリート製のパーツに表情が生まれる。
但し、開孔による部材強度への影響は如何程か。
例えば同じ工業製品であるところの孔開きコンクリートブロックにも当て嵌まることだが、意匠に凝ることと生産性ないしは性能の確保はトレードオフにならざるを得ぬ。
右の事例は、坂道に設けられたもの。
道路の勾配に合わせて柱間のパネルも傾斜させて嵌め込んでいる。
これは、万年塀だからこその適応性。
坂道に合わせてパネルの両端を現地で切削し柱間に落とし込めばよいのだから、どんな勾配にも容易に対応出来ることになる。
近年は、プレキャストコンクリートに替わり、鋼製の柱と木のパネル材で構成する万年塀も製品化されている。
軽量化によって施工性の向上と地震時の倒壊リスク低減が期待出来るだろうし、あるいは木による柔らかな表情の付与も可能となった。
外構工事のニーズにあわせ、当該部材も様々進化している様だ。
|

|
|

|
|
|
2020.04.30:メーカー住宅私考_115
|
|
|
|
|
ウェブ上の配信サイト「note」に、竹内孝治さんという方が「住宅産業論ノート」というタイトルで住宅産業についての興味深い論稿を多数発表していらっしゃる。
いずれも個人的に興味が被る内容で、最近投稿された「フリーサイズからホームコアへ|住宅産業の異端児・ミサワホームの1960年代」もとても楽しく拝読した。
内容は実際に氏のnote※1を読んで頂くとして、私なりに感想を二点。
まずは、論稿の最終章のタイトルとして掲げられた「1960年代、ミサワホームはヘンタイだった」。
これに対しては100%同感である。
そしてそのヘンタイっぷりは80年代半ばまで続いた。
当時の私が同社の商品群にハマったのも、結局のところはその変態性に他ならぬ。
但し、どんな産業であれ、ヘンタイがヘンタイとして奔放に立ち振る舞えるのは、その分野の成長期だ。
安定期・成熟期に入ると、ヘンタイのまま尖がり続けることがなかなか辛くなる。
住宅産業の場合は、80年代半ば以降がそれに該当しよう。
ために、私の関心もその時期に一旦途絶えた。
もう一点、論稿の主旨である同社の「逆張り」性について。
自由で質の高い造形性から出発し、高度な工業化路線へと突き進んだ同社の60年代の動き。
それは、生産性重視から商品性重視へと進んだ他社の動向とは「逆張り」であるとする解釈は、確かに可能だ。
しかし私はヒネクレ者ゆえ、異なる考え方を無理矢理捻り出してみることにする。
当時の同社において、高い造形性と高度な工業化は、一つの線上に時系列として並べられ得るものなのか。
否、同社にとって両者は常に並列だったのではないか。
他社を圧倒する高い技術開発力に基づき住宅生産の工業化をガンガン推し進めつつ、同時に高い造形性を志向する「作品」も積極的に発表する。
だから、工業化住宅の精華としての「ホームコア」を発展させた「未来住宅・ヘリコ」を大阪万博(EXPO'70)に出展しながら、住宅作家顔負けの斬新な造形性を持つ「ハイリビング」を同じ年に開催された第一回国際グッドリビングショーにて発表する※2。
あるいは、オイルショック以降、規格住宅改め企画住宅の傑作を怒涛の如く発表し続けながら、総合カタログにはそれらと一線を画す渋めの和風住宅※3等の自由設計事例が併載された。
 ミサワホーム・ヘリコ外観
ミサワホーム・ヘリコ外観
|
|
 ハイリビング外観
ハイリビング外観
|
この様に、相反する二つの方向性について、同社はかなり戦略的に両睨みの立ち位置をとっていたのかもしれぬ。
単純に言うならば、ホームコアから和風住宅まで、何でも最高品質で実現して御覧に入れます、である。
そしてその鮮やかな二刀流は、筋金入りのヘンタイであったからこそのなせる業であった、という見方はどうだろう。
好き勝手なことを書き散らしてしまった。
竹内さんが展開する「住宅産業論ノート」の論稿を、今後も楽しみにしたい。
|
※2:
第一回グッドリビングショーについて、中外出版がかつて出版していた専門誌「建築」の1970年11月号に石山修武と大野勝彦の対談が掲載されている。
このイベントに出展された多くのモデルハウスは、ユニット工法が用いられていた。
敢えてこの工法に拠らぬハイリビングを出展したミサワホームのことを、御両人共に「あれはうまいと思う」と評している。
このあたりは、同社ならではの「逆張り」であったと言えるのかもしれぬ。

※3:

自由設計による和風住宅の例。
この住宅については、メーカー住宅私考の第33回(2013年10月17日)及び第35回(2013年11月18日)でも言及している。
同社の商品体系の変遷における位置づけがとても興味深い事例だ。
|

|
|

|
|
|
2020.04.26:メーカー住宅私考_114
|
|
|
|
|
ハウスメーカーの中で、地下室を提案した最初のモデルはどれだろう。
そのことについてあまり深く追求したことは無いが、例えばミサワホームが1976年9月に発表したミサワホームO型にはオプションとして半地下空間が提案されていた。
それはジメジメとした地中の密室ではない。
サンクンガーデン(空堀り)を介して地上の光や大気と繋がるものであった※1。
既に同年4月開催の東京国際グッドリビングショーに出展された同モデルのプロトタイプに、その様な空間が設えられている。
恐らくは最初期の試みだったのではないか。
後継モデルのOII型のパンフレットではホームバーとしての活用がストーリー立てされ、敢えて低い天井高にピット式の固定テーブルを設えた非日常空間を紙上に演出していた※2。
そこには、将来予測として当時想定されていた週休二日制の定着による自宅内で余暇を過ごすライフスタイルの一般化を先取りした商品提案の意図が込められていたのであろう。
但し、全国いたるところでその建設事例を見掛けるO型シリーズに関し、このサンクンガーデンを組み込んだ地下室付きの事例に出会ったことは残念ながら未だに無い。
高床形式の事例は豪雪地域を中心に幾つか見掛けているが、その場合はいずれも駐車場か物置の用途に供されている。
同社の総合研究所がウェブ上に公表しているテクニカルレポートVol.63「地下室付住宅」においても、
|
上屋は爆発的なヒット商品となったが、地下室付の実需はほとんど無かった。
|
と記述されている。
昭和50年代における事例として、他にも三井ホームから「スペースクリエーション」、第一木工(現、GLホーム)の「ギャラリーII」が挙げられる。
双方ともに、屋内にスキップフロアを大々的に取り入れた多層構成の中に半地下を組み込んだもの。
ギャラリーIIについては最近千葉県流山市内で中古住宅を内覧する機会を得た。
但しその事例では、半地下では無く一階レベルに半分の階高のいわばピット空間としての物置を装備したものであった。
他にも、三井農林の「1200シリーズ」や大和ハウス工業の「ホワイエのある家」でもサンクンガーデン付きの地下、ないしは半地下が提案されていた。
更に、殖産住宅工業の「ミセス・ピアシリーズ」では、サンルームを介して一階のリビングルームと吹抜けでつながる大胆な空間構成の地下室が提案されていた。
ほかにはどの様な提案モデルが在ったのだろう。
あるいは実際の建築事例及びその使われ方と現在の状況について等々、興味がわく。
|

|
|

|
|
|
2020.04.21:選手村
|
※1:
 若潮ハイツ。
若潮ハイツ。
総戸数500戸の規模の大きい団地。
|
|
|
少し前の日経アーキテクチュア誌に、完成に近づいた東京・晴海の五輪選手村に関する特集が組まれていた。
冒頭の空撮画像からは、板状箱型の住棟が高密度に並ぶ様態が窺える。
ややめまいを覚えそうなその連なりからは、全てタワーマンションで計画してしまえば、周辺の景観とも調和がとれたのではないか、という印象を単純には持つ。
しかし実際には、選手村としての運営とその後の分譲にあたっての様々な事業スキームを考慮した結果が現況なのだろう。
その策定プロセスはどんなものだったのかということには少々関心が向く。
記事によると、この大規模な整備事業には多くのデベロッパーと建築家が参画している。
その取り纏め役を担ったマスターアーキテクトへのインタビュー記事の見出しに「個性と統一感は共存できる」とあった。
その実現のため、会合を幾度も重ねて棟ごとのデザインの調整が図られたことも言及されている。
しかし、集合住宅という用途において、デザイナーが関与できる範囲は極めて限定的だ。
配棟計画も各棟の住戸割りも、そして住戸内のプランニングも、それらの最適解を導き出す策定技術は洗練を極め且つ一般化している。
人の手や技能的な修練に拠らずとも、AIにて全て代替え可能となるのはもはや時間の問題。
ある意味硬直化してしまったその手法の桎梏に在って、彼等が介入出来るのは外観ファサードや共用エントランス廻り等の意匠に限られることとなる。
とりわけ外観に関しては、バルコニーに限定される。
同誌において、各住棟のバルコニーを撮った写真を比較し易いように並べた見開きのページがある。
それは結局、デザインに関しそこしか語る要素が無いことの表れでもある。
バルコニーの先端にイミテーションの竹をランダムに配すとか、あるいはウネウネと曲面を描くガラス手摺を巡らすとか、限られた条件下でそれぞれに個性は追求された様だ。
しかしそれらは、遠目には枝葉の問題にしかならないのかもしれぬ。
果たして個性と統一感を共存させた景観はどの程度成立したのか。
その点については実際に現地を拝んでみたい気もする。
数年前に千葉県の海浜ニュータウンを散策していた折、少々年季の入った団地を見かけた。
調べてみると、若潮ハイツ※1と名付けられた13棟の低層住棟が連なるその団地は、1973年に県内で開催された若潮国体の選手村として整備され大会終了後に分譲されたものであった。
大規模なスポーツイベントに関わる施設に対し、「レガシー」という言葉が頻繁(というか、安直)に用いられる。
建設から約半世紀を経た当該団地を見て、このレガシーということについて考えさせられた。
と同時に、晴海の選手村についても、半世紀後に想いが至ることとなる。
これは気の早い話でも何でもない。
新築という行為に、その後の修繕や解体を含めたライフサイクルが関らないという考えはもはや有り得ぬ。
ちなみに、若潮ハイツは現在建て替え事業が進行中だ。
|

|
|

|
|
|
2020.04.14:【書籍】営繕論
|
|
|
|
「希望の建設・地獄の営繕」というサブタイトルが気に掛かり、読むのを躊躇していた。
「地獄」という単語に、ひたすら鬱屈を強いられる論説の展開を単純に想像してしまったためだ。
ところが最近、図書館にて同書が目が留まり、試しに手に取ってみた。
目次を見ると、最終章のタイトルは書名とは真逆の「虚構の建設・希望の営繕」とある。
「虚構」という文字に、これまた鬱展開を連想しなくもない。
しかし、一方の「希望の営繕」とは何ぞや。
更に、ページをパラパラとめくってみると、終盤の方で乱雑に電線が這う電柱が立ち並ぶ風景写真が載せられている。
この画像と営繕の関係は何か。
そんなことに興味を持ち、借りてみることと相成った。
内容とは直接関係無いけれど、同書に連なる文体の特徴として、「〜を糧に〜」という言い回しが結構目に付く。
頻度としてそれほど多いということでは無い。
でも、気になりだすとそれなりに目に留まる様な気がする。
そんな枝葉な点はともかくとして、営繕に纏わり書かれている内容はとても示唆に富んでいる。
図書館で手に取った際に目に留まった電線の画像に関する論述が展開する第9章「保全性の現在」などは、配線に纏わる筆者のフェティッシュな視点が見て取れて特に面白い。
そこから営繕の話に繋げる文章の組み立ても、そして同章に至るまでの各章の言説との繋がりも実に見事だ。
しかし、電線の細部に如何なる拘りや機能が宿っていようとも、そこに美を見い出す価値観は一般に広く共有し得るものではなかろう。
あまつさえ、道路沿いに並ぶ街路樹に電柱や電線が見え隠れするアングルの画像を提示して、それらが景観を大きく阻害するものでは無いと主張されても何だかなぁという印象ではある。
果たして一般的な美に対する価値観と切り離して営繕の希望は成立し得るのか。
否、同書で書かれる「信頼性」と「保全性」という二律背反な課題を用途や機能や目的に応じてバランスさせつつ、更にそこに美を介在させること。
そこにこそ、営造と修繕の総体としての本来の「営繕」における希望が見い出せるのではないか。
あるいは「美しきもののみ機能的である」という近代建築における代表的なテーゼ(の一つ)に対する現代の応答となり得るのではないか。
今後の業界の状況が「衰微の建設・諦念の営繕」なんてことにならぬように、個々の事業の在り方について考えてゆかねばならぬ。
|

|
|

|
|
|
2020.04.06:円形校舎
|
※1:
 石狩市立石狩小学校外観。
この校舎については2010年8月16日の雑記でも言及した。
石狩市立石狩小学校外観。
この校舎については2010年8月16日の雑記でも言及した。
|
|
|
建築探訪に登録している室蘭市立絵鞆小学校のページを更新した。
昨年開催された一般公開時に撮影した内観写真の追加が主だった更新内容。
一般公開は、当該小学校の建物の特徴である二連の円形校舎のうち、体育館を最上階に配した体育館棟の解体決定に伴い催された。
解体理由は、老朽化及び閉校後の利活用の目処が立たないことに拠る。
ちょうどお盆休みに開催されたのは、同市に帰省する卒業生のことを配慮してのことであったのだろう。
私はOBではないけれど、たまたま道内に帰省していたため、とても貴重な機会だと思い同小学校を訪ねることにした。
北の大地とはいえ、盛夏。
苛烈な暑さの中、しかし円形校舎の屋内はどの場所にいてもどこからともなく微風がそよいで来る。
これは、全方位に外部開口が途切れることなく連続し、そして建物中央を縦に貫通する螺旋階段を介してペントハウスへと通風経路が確保されていることに拠るものなのかもしれぬ。
実際に訪ねてみなければ経験し得ぬ事々に触れながら、そしてこれが見納めかという感慨にも浸りつつ坂本鹿名夫の設計による円形校舎を堪能した。
見学会の三か月後、除却する予定となっていた体育館棟について、その方針を見直すべく検討に入った旨が報道された。
解体を取りやめ市民団体に売却。
市による活用が決定しているもう一方の教室棟と共に二連の円形校舎が存続することになったのだそうだ。
「建築探訪」のページでも書いたが、二連の円形校舎は構成原理を共通としながらも内部用途の違いからやや異なる内外観を呈している。
そんな、似て非なるもの同士ながらその逆も然りという絶妙な相補関係の両者が並置されてこそ、そこに建築としての価値が見い出せる。
だから、二棟の存続はとても喜ばしいことだ。
建築探訪の方のページ作成にあたって参考資料とした学会論文「北海道における円形校舎について」によると、道内には11件の円形校舎が建てられ、そのうちの8件が坂本鹿名夫の設計による。
いずれも昭和30年代から40年代に建てられ、その後閉校若しくは除却されたものは少なく無い。
今、現存する校舎は如何程か。
例えば小樽市に残存する小樽市立石山中学校は、絵鞆小学校と同じく体育館棟と教室棟の二連で構成される。
そして教室棟の方は5階建てという規模。
先の論文によると、二連構成の円形校舎は当該中学校が国内初の事例とのこと。
閉校して20年弱を経ているが閉鎖されたままであり、接道する校門から山道の様な上り坂を介して至る高台に立地するために敷地外近傍から外観を仔細に確認することは叶わぬ。
今後の扱いが気になる円形校舎だ。
また、坂本鹿名夫の設計によるものではないが、道内では最後の現役円形校舎であった石狩市立石狩小学校※1も、この三月末をもって閉校した。
市内初の鉄筋コンクリート造の建物であり、その形態から地域住民に「缶詰校舎」と呼ばれ親しまれていたそうだ。
|